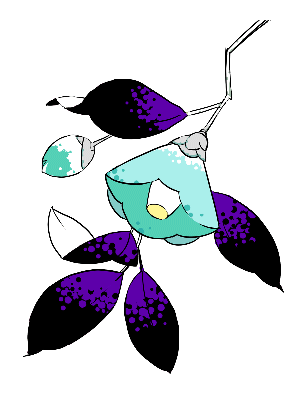
大坂での合戦は大方の予想通り徳川方の勝利となった。それもそのはず、大半の諸将が家康に付いているのだから必然だ。ただその中で、武田の遺臣である真田が出丸を築き奮戦し、徳川方にかなりの痛手を与えたという。
「真田殿……」
彼もまた家康を拒絶した一人だという。武田の為、己が信念の為、我々は似ているのかもしれない。その戦ぶりをこの目で見て支えたかった。
だがその出丸も和議の条件として埋められてしまったという。それどころか大坂城は二の丸三の丸共に破却されその資材で堀を埋められてしまったと。今の大坂城は丸裸、秀吉様がご覧になられたらなんと仰るだろうか。
否、それどころでは無い。和議如きで終いではないはずだ。年もおかずまた大坂は攻められる。その時は間違いなく最期を迎え、残った若君、女君らと共に真田殿も葬られるだろう。
今一度、向かおうにもこの腹では動けそうになかった。まだ出ておらぬ腹は今は騙せるが、次に大坂をとなったときにはもう無理だ。家康に隠せず、この身はもう……。
「浪速のことは、夢のまた夢……秀吉さまが仰るとおりになってしまった」
障子に手を遣って外を見る。相変わらず冷えた庭に芽吹くものはない。格子はないがその先には幾人かの気配がしてやはり逃げるのは難しかった。
そのまま障子に凭れて座りあてどなく眸に景色を写す。心をどこかに遣ってしまいたいのに時折喉元を抉るように嘔気が襲い来る。この身は、どうして。
その日の空はなんとも言えないもので、寒々しく曇ったかと思えば突然の晴れ間を出す、晴れたかと思えばその間から雪も射す、不可思議な空模様を繰り返し宵を迎えた。
一旦江戸へ向かった家康が未だ戻らぬ闇夜、寝付く気にもならず書冊を手に取った。どうすれば堀のない大坂城で戦えるか、一矢報えるか、当ては無いが調べずにはいられなかった。
早々に侍女を下がらせ衣擦れの音が去ればジリ……と灯明皿が僅かに音を立てた。この静寂に書冊をめくる音、そして墨を磨り筆を走らす音、これが夜の供だった。
今宵は一等頭が冴える。書冊の葉(えふ)を捲れば捲る程策が浮かぶ。ただ共通するのは籠城があり得ないということだけ。あちらもあの真田殿がいれば分かっているはずだ。
半時も経った頃か筆を置いて襖を抜けその先の障子を開けた。暗き空に見えるは満天の星だ。綺麗だと思う。吸い込まれてしまいそうで。
「このまま消えてしまいたい?」
「――!?」
不意に聞こえた声は誰も居るはずの無い後ろからで、だが自分の心内を移すものだった。息を呑んで振り返ると襲い来るように記憶が呼び起こされる。この声、この顔確かに見たことがある。
「貴方……真田殿の」
「そー、覚えててくれた? 鴨跖草の、竹中の旦那の愛(めぐ)し子さん」
戯けた口調に優男な顔つきだがその身は鋼のような筋を持つ、わたしはこの男の人となりを知っている。真田幸村の腹心で服部半蔵に勝るとも劣らない忍び、名は猿飛佐助、大坂の城で数度話したことがある。あの時何故気づかなかったのか。
「その声は、先日の……」
「あ、やっぱ分かっちゃった?」
「今思い起こせば、ですが。此処には見張りが多数いたはずです。あの服部半蔵も」
「あーうん、みんな仲良く寝てもらってるよ。戦国最強がいないことが幸いしたね」
仮にそうだとしても、彼が寝ていると言った忍び達が倒れる音すらしなかった。やはりこの男はしのびの中でもかなりのものだ。はやる心臓に静まれと念じ障子を閉め、外から見えぬように襖の奥へと戻る。
「あー、悪かったね。あの時やっぱり逃げられなかったんだ」
「城から出ることは出来ましたけど伊勢で連れ戻されてしまいました」
「そっか、ごめんね。半蔵の旦那とやり合った後、本多の旦那が来てさ、結構深手負っちゃってあんた拾って逃げることが出来なかったんだ」
「総てはわたしの不甲斐なさです。……あの時どうしてこの城に?」
なるべく明かりから遠ざかって座ると彼も同じように離れた場所に立つ。
「大坂方の時間稼ぎしたいのと、駿府の城の佳人が知らぬ顔の半兵衛が残した一葉じゃないかって噂があってさ。調べてみたら鴨跖草殿の墓は空っぽだし、ついでに見てみるかってね」
「真田の副将は優秀だわ」
「雰囲気、変わったね。で、此処でなにしてるの? 豊臣と徳川の最後の戦が始まるよ」
「もう次の目処を徳川は立てているのですか」
「いつだと思う?」
「出来て半年後かと」
「流石鴨跖草殿だね、衰えてないか。うちの大将とおんなじ事言ってるよ。さあ行こう、……って言いたいけれど随分様変わりしたね」
「……」
「やつれたのに見た目にも身が柔らかくなった。戦が出来る身体じゃないね」
「……猿飛殿にはお見通しなのね」
忍びは肉体も思考も感性も発達している。如何に天候を読み戦流れを読む軍師であろうとその感には敵わない。何があったかなどすぐに分かったことだろう。その証拠に彼はもう一度小さくごめんね、と呟いた。
「我が身の情けなきことです」
「女の子が戦って生きるってのはなかなか難しいことさ。俺の知ってる子も身を削ってるよ。止めりゃいいのにさ。でもその子もおたくも譲れないもんがある、それは分かってるつもり」
彼は部屋を見回し彼特有の気安さで調度品に触れる。高価な櫛も香炉も我々には無用だ。茶入のひとつを手に取り指先でくるくると回しながらかの忍びはわたしの前にしゃがみ込んだ。
「それで、今からどうしたい?」
目を見開き彼を凝視する。皮肉屋っぽく笑んでいたが佐助の眸もまたかすかな哀切を帯びていた。
……部屋の中にいるのに、一条の光と共に風が吹いた気がした。脳はキンと冷えた氷のよう。
猿飛殿、わたしにそれを選ぶ権利がまだあるのですか。望んでも望んでも首を横に振られ断られ続けた願い。今戦力が欲しい大坂方の貴方がそれを許してくれるのですか。
ああ、溢れてくる。泪が止まらない。
「この生を終わらせたいのです」
「そう、わかった。俺様が殺してあげるよ」
聲があまりに優しく嗚咽を堪えるのに必死だ。彼はわたしの頭を撫でて、それがまた在りし日の師を思い起こさせる。
「俺もさ、知ってんだよね。あんたみたいに過去が幸せすぎて利害なんか関係なくそれを追っかけちゃう人をさ。危なっかしくて見てらんないよまったく」
「その過去は……きっとその方の命の花なのです。散れば何の意味も無い……」
「そうかな? 散れば実がなり、未来が出来ると思うんだけど」
「猿飛殿、ならば貴方の主君や貴方も、花の時よりも先を望みますか?」
「さて、ねえ……」
彼の立場ならば付いていく者らの為に生きるという選択肢を選べ、と言えただろう。茶を濁す配慮をわたしは忘れてはならない。
静かに目を合わせると彼はわたしの肩に手を置いた。打ち損じないようにする為だ。
「大丈夫、きっとあの軍師のところへ逝けるよ」
「いいえ、誰が許してもわたしが許せないの。このような身であの方に合わせる顔なんてない……」
「そんなこと言わないと思うよ、きっとね」
その台詞は偽善に他ならないのだが総てがしみ入るように耳を撫でた。
「お腹は、刺さないでくれる?」
「そう望むなら」
「……おかしいわね、家康の子なんて絶対許されないって思っていたのに、女の自分なんて持ち合わせる気はなかったのに」
「いいんじゃない? 女じゃなくても、母の気持ちは持ってもさ」
「感謝します」
「なるべく痛くないようにするから」
「ふふ」
「ん?」
「わたしの袖はあれから泪以外に濡れることはありませんでした……」
「あんたよくやったよ。……実際がんばっただろ? あの孤立無援の中でさ、みんな家康様は間違ってない、そんな感じだもんね」
「貴方は優しいのね。……皆、今参ります……」
小さく頷いて手を合わせ、先に泉下へと向かった者らの名を呟く。脳裏を駆け巡るのは師の笑み、雄々しき主君、剣先のように鋭い同僚、謎かけをする不思議な同輩、賭け事に目が無くてでも憎めない後輩の顔……ああこれが走馬燈というやつかなんて思った時、首だか胸だかによく分からない衝撃が走り視界は赤か黒か判別せぬうちに霞んでいった。
――なのに、最期に浮かんだのはわたしを苦しめたはずの家康が手を差し伸べる姿だった。
ああ、わたしは、たぶん……、