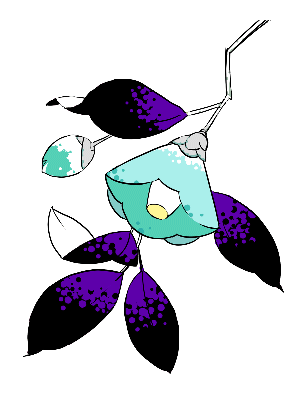
眉間の皺をどうにかしろ、といつも主君に言われる彼だが駿府から齎された書状には一段と眉を顰めるものでしかなかった。自分がそういう顔をすると大概茶化す主君も今回ばかりはなんとも言えない表情のままかわほりを持て余す有様だった。
二の丸殿、かつての鴨跖草の軍師が頑なに家康を受け入れないのは伝え聞いている。半端に関わってしまった者としては気にもなるし、拒否も出来そうにない。結局、さして断る理由もないことから相手の望み通りに駿府城を訪れた片倉小十郎だがどんな顔をしていいものか分からないでいる。
すでに主君は家康と話があると本丸に詰めてしまい、その東照からも、頼む、と一言念押しされて逃げ場もない。二の丸御殿に近づくにつれ白粉の香りが増すようでますます居心地も悪かった。
「なんで俺なんだ」
先導する近待の若造が困惑した顔をみせたがその表情には哀れみも含まれていて一層気が重い。承服しかねても終わらせるしかなさそうだと歩を進める。
「此処もそれなりに冷えるな」
そう呟くと、それが今から会う女の胸中のように感じられ、埒もないと首を振るのだった。
約二年ぶりの再会は片方には驚きを、片方には懐かしさを齎した。
片倉小十郎は露骨に目を見開き居心地の悪そうに用意された茵に腰を下ろした。その相手に媚びない所作はあの頃と何ら変わりは無い。
「片倉殿、御足労頂きありがとうございます」
「鴨跖草の、何故俺を呼んだ」
「さあ、何かをしろと言う訳ではありません。ただ主君を持つ軍師の貴方に聞いて欲しかったのかもしれません。……伊達殿はわたしを生かす話を知って家康に協力したのでしょう? 貴方も傍で見ていたはず。なら、少しぐらいわたしの愚痴に巻き込まれて下さい」
「てめえにゃ余計なお世話だったろうな」
「途方もなく」
不機嫌そうにみえる竜の右目に周りの侍女たちは萎縮している。興が削がれる、と強めに言って人払いをすると彼は些か眉をつり上げた。
「貴方と初めてお話したのは大坂ででしたね」
「ああ、竹中半兵衛の後ろに大した剣も振るえなさそうな小娘がいるから何者だと思った覚えがある。あれが鴨跖草の軍師だと聞いて随分驚いたがな」
「貴方はあの頃とお変わりありません。主君以外に必要以上の礼を取ろうとしないその潔さ、わたしも見習うところでありました」
「見習われるようなことじゃねえ。俺はただ政宗様と奥州以外に価値を見いだせなかっただけだ」
「本当にお変わりありません。……あの頃はわたしも我が世の春でございました」
「そうだろうな。あの頃のおまえは幸せそうな顔をしていた。自分の存在意義を見いだして誠を尽くす、そう見えた」
ああ、偶然ではなく必然であった。同じ軍師であるこの男がわたしのなんたるかを知る者であったのだ。だからこの男を呼んだのだと伏せる瞼は震えて鼻の奥はつんとなる。
「片倉殿、片倉殿の人生の始まりはいつですか?」
そう問うと竜の右目は眸を見開いたが、やがてゆっくりと噛み締めるように瞼を閉じる。
「……そうだな。先代輝宗様に拾われた時だな」
激すれば鬼神のようだとも聞く男だが再び開いた双眸は澄んで美しいと思う。
「俺は片倉の後妻の次男坊だ。実家の神社は先妻の長男が継ぐ。だから養子に出された。だがなかなかどうして、養子先に子が生まれて俺は不要となって実家に戻されちまった。姉が彼是と守ってくれはしたが子供心に肩身が狭えったらなかったぜ。そんな時だ、輝宗様にお声掛けを頂いたのは。……世界が変わった、そう思ったぜ」
「世界が、変わる……。わたしもそう、半兵衛さまに見つけて頂いた……」
「そうか、てめえもか」
「昔話、聞いて頂けて?」
「ああ」
何故この男は怖いと言われるのだろう。こんなにも懐の深い優しい殿方なのに。
「わたしの父母は早くに亡くなって家督は叔父が持って行きました。先代の娘としてそれなりの生活はさせてもらいましたけど女が兵法書を読むのはいい顔をしなかった。そのうち従兄より兵法に明るくなるとさらに。それでも女子としての教養はそれなりに身につけていましたから取り上げられることはありませんでした。気持ちは窮屈だったけど感謝はしていたわ」
ゆっくりと思い出しながら一言一言を紡いでゆく。片倉にもそれが分かるのか彼はなにも言わず聞いている。
「でもある日、西の大名のお偉い方が屋敷に来られるとなった時、叔父は何故かわたしの書いた陣立て表を持って行きました。遅れてお客様に挨拶をしに参ったら叔父がその陣立て表を従兄が書いたものだと嘯いているところでした。その時理解したんです。叔父はわたしをこのように使うために屋敷に置いたままにしといたのかと」
そっと侍女が持ってきた湯飲みを一撫でする。僅かに揺らいだ波紋がわたしの心を現すようだ。
「ですけどね片倉殿、そこに居た銀髪の綺麗な御方はすぐ偽りを見抜かれた。従兄に、大胆な陣配置だね、どういう意図で差配したの? って。当然従兄は答えられなかった。それを見てすぐにわたしの方を向かれて、これを書いたのは君だろう? 此処の家に兵法好きな女の子がいることは知っているよ。それにこれは女の字だからすぐに分かったよって。わたし、全部答えました。配置の意図とそれによって予想できる動き。そしたら真剣に聞いて下さって、じゃあここをこうすればもっと効率的に動くよ、ここの配置はちょっと甘いね、って丁寧に教えて下さって。屋敷の者とそんな話をすることも無かったからとても嬉しくて楽しくて。このままこの人が連れて行ってくれないかなとまで考えました。帰り際、お茶を飲みながらその方は、半兵衛様は仰いました。この子を連れて帰るって。立派な軍師にしてあげるよって」
あの時の一言一句を思い出して口にすれば目も口許も緩む。あれが幸せの始まり、色褪せることのない日々の始まり。
「嬉しかった、初めて認めて貰えた。おいでと手を差し伸べられた時二つ返事で頷いてその手を取りました。後ろをみたら叔父が随分恨めしそうな顔をしてましたけど躊躇はありませんでした。裏切られたことよりもわたしを理解して下さった方を謀った人に遠慮することは無いと思った覚えがあります。後から知りましたけど叔父はゆくゆくわたしを従兄と縁付けるつもりでいたようです。どうせ女が学を持ったところで認められやしない、行き場などないのだからその才を夫の為に使えば良いって。笑ってしまうわ。……半兵衛さまが見つけて下さらなかったらわたしはきっと従兄の妻にされていたんでしょうね」
紡ぎながら思うのは、それは今の状況と似ているのでは無いかということだ。このままここに居たらわたしはやがて家康の為、子が生まれたら子の為に知略を使わざるを得なくなる。
しかし瞼の奥ではあの日わたしを拾って下さった白藤の軍師の柔らかい笑みが浮かび幸せだった日々が甦る。
「わたしの人生の始まりもまた半兵衛さまに拾って頂いた時」
「幸せそうな顔をする。てめえがどれだけ竹中の野郎を敬慕しているかは分かった。だから竹中を裏切ることもねえのもな。俺にも覚えのある感情だ」
「いかに主家が滅ぼうと靡くことはありません。わたしも、あなたも」
「ああ」
そこで初めて竜の右目は微笑んだ。尽くす相手は違えど軍師として互いに命を掛けた者へ向けた笑みだったのかもしれない。
だからこそ彼に頼みたい。茵から降り深々と平伏して告げた。
「片倉殿、後生でございます。どうぞその懐の短刀をわたしにお与え下さい」
「お前……」
「最早わたしは軍師には戻れません。ならば命の終わりは自分で決めたい」
このまま居れば家康に陥落するのは目に見えているし拒んでも膨れてくるであろう腹がそれを許さない。
彼はひどく動揺した顔を見せたがややあって首を振った。
「……だめだな。お前は徳川の閨に上がろうと思えば上がれる人間だ。その短刀がてめえの身ではなく徳川を貫いたら、それこそ乱世に逆戻り。それだけは避けなきゃならねえ。政宗様もそれはお望みにはならねえだろう」
やはり、分かっていた答えだった。泪が出るのに笑みも溢れた。
「やはり片倉殿はひとかどの軍師でいらっしゃいますね。半兵衛さまが見込んだ通りの御方です」
ご息災で、と言えば彼も小さく頭を下げて立ち上がる。きびきびとした所作で去って行く彼の背中を追う。幾多の戦場を駆け巡り折れることの無かった男の背だ。とても憧れて得ることの出来なかったもの。
一つだけ彼に聞かなかったことがある。それは、
『もし自分が三成や刑部辺りに嫁いでいたら関ヶ原で一緒に死ねただろうか?』
ということだ。おそらく彼はこう答えるだろう。
『それは無理だな。死に臨む直前に捕らえられて同じようにこの御殿に置かれたろうさ』
と。
彼の代わりに開けた障子から冷たい風が入ってくる。足の先からキンと冷えたが今の自分にはお似合いだと思えた。
翌日、伊達軍は駿府を発ちその数日後にはまた家康も出立した。行く先は大坂だ。