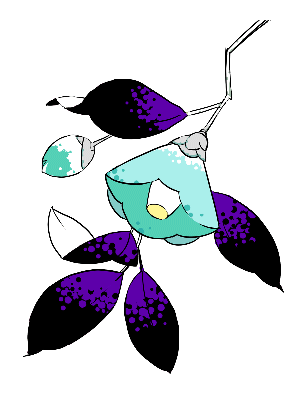
青天の霹靂――
波乱に富んだ生を貪る中でそんな状況には何度も遭遇した。だが、今回は一等だった。聞かなければよかった。知りたくなかった。
「え? 二の丸様が?」
「そう、お気づきではないみたいだけど」
それは身体が思わしくなく寝込みがちになった昨今、わたしが眠っていると踏んで話し込む侍女たちによってもたらされた情報だった。
障子越しに聞こえる声は、白粉の香りのする侍女ともう一人、毎日聞き知ったものだ。
「もう一月以上、月のものがおありにならないの。外に出られてるときにおありになられたかもしれないけれど……」
「え、なら、先日昏倒なさったのは」
「多分そのせいね。身籠もると気の道も弱るというし、近頃はよくぐったりとなさっておられるし、その時診られたお匙もそのように仰ってたわ。でもね貴女、これは内々だけのお話よ。まだ本丸にも話が行っていないの。家康様はきっと大喜びになられるだろうし、それで二の丸様が感づかれたら……」
「今度こそ危ないですね」
「お可哀想だけど、ね。こっそり二の丸の人員も増やしているの。お勤めは忙しくなるけどお互い気を抜かずに頼むわ」
「心得ました」
このような会話であった気がする。彼女たちがいつ去ったかは知らないが、脈打つ心臓も呼吸もひどくゆっくりで永遠のようにも感じられた。
「嘘でしょう……」
地獄に墜とされるとはこのことだ。そうあってはならないことがこの身にとうとう起きてしまった。自身の不甲斐なさを詰り、泣き叫んだところでこの事実は変わらない。
口にするも悍ましい”懐妊”の二文字。もう寒い季節だというのに汗が伝い喉が渇いた。絶望以上の言葉が存在するなら誰かわたしに教えて欲しかった。
今はただ永遠の闇の淵に墜とされたような、出口などもう無きに等しい。
盗み聞いた会話の通り、二の丸の侍女たちは忠勝にも適当な病名を告げたようだ。
忠勝から知らせを受けた家康が慌てて来たがわたしは泣いて取り乱して家康とは襖越しに話すのみだった。あれ以来彼を受け入れてはいない。たった一度、たった一度のことであったのに巡り合わせというのはなんて皮肉なのだろう。
今日も彼は訪れている。その聲を聞くだけでわたしはとても心が苦しいというのに。その優しさが、わたしを追い詰めるというのに。
「」
「今日も来たの」
「外は冷えるが少し歩くか? もう格子を取り払っていることに気づいているだろうか。庭を歩いてみないか」
「そう、格子外したの……いいわ、身体が痛くてあまり動きたくないの」
本当は吐き気が酷いのだが、ここでそう言っては侍女にも家康にも勘ぐられる。そのまま脇息に凭れれば身体を壊した女の出来上がりだ。
「瘧か血の道の病だと聞いたが……」
「長年無理をしていたからだと言われたわ」
「然もありなん、だ。不本意だろうがゆっくり養生して欲しい」
「ええ。……家康」
「ん?」
生唾を飲み込めば音が酷く耳に残る。動揺も恐れも一緒に嚥下してしまえと続けた。
「あの日のわたしのことはもう忘れて欲しいの。あの日のわたしは間違いで起こったことも間違いだわ」
ついでに今のわたしも間違い、そう告げるのは止めた。しかし襖の先でピンと線が一本張った気がしたと思えば幾分低くなった家康の聲が耳を突く。
「、ワシは――」
間があって、彼が身じろぎする衣擦れの音がし、次いで聞こえたのは憤懣遣る方ない吐息を大きく吐いた音だ。雲行きの怪しさを感じ脇息に凭れて居ない掌を胸元でぎゅっと握りしめれば傍に控える侍女たちも息を呑んだ。二の丸様、それを申し上げてはなりません、彼女たちの目がそう言っている。
刹那、乱暴に襖は開いて耳障りな音と共にすぐ傍の調度品たちも取り払われる。
「――っ」
「な、内府様っ!」
「家康様っ!」
侍女や近待の制止よりも、横に退けられるお飾りの几帳の隙間から見えた家康の眸に目を奪われる。戦場でも大坂でも、今日までの駿府でも見たことのない鋭いもので思わず身が竦んだ。
それでも逃れようとすると、几帳からは家康の手が伸びて、脇息に凭れていないほうの手首を掴まれる。
「……あっ!」
「そんな声も出る人なのにおまえは……」
射竦める視線と絞り出すような声がわたしを搦め捕るのだ。
「、ワシは――あれは間違いではないと思ってる。勿論ワシの言葉も行いも褒められたものではないが、という人が心の内を初めて披瀝してくれた日ではないか」
「やめて」
女ではなく人と言った。これが彼の心遣いなのだろう。家康はこうやって相手の心に入ってくる。だからわたしは何度も何度も拒絶するのだ。一度身を許したのだからとずるずるいってしまいそうな気がして。
賢い人間なら此処でこんな話をしなければいいのだ。もう流れに身を任せて受け入れれば良いのだ。
「、、泣かないで」
打って変わって家康の眉が下がる。ああ、わたしは泣いているのか。家康は危険だ。声も仕草も、何もかも。わたしを麻痺させる劇物だ。
天下人の切ない恋模様は軍師としてのわたしをどんどん摩耗させていく。その事実に身震いして眩暈を覚えるが、今この瞬間さえ蹌踉めくこの身を支えるのは家康なのだから心は矛盾に苛まれ続けるしかない。
「すまない、顔色が大分悪くなってしまった。――腕も、細くなってる。分かっているんだ誰のせいかくらい」
眩しいのだ。この男は。
「悪かった。気分を変えよう。外が無理なら何か見たいものはあるか? 欲しいものはあるか?」
何もないのよ家康。わたしが欲しいものは駿府にはないの。関ヶ原の時に置いていってしまったの。置いて行かれてしまったの。
小さく首を振るばかりの女にいよいよ重い病と思っているのか彼は掴んだ手をそっと戻して、乱れ箱から打掛を一枚取り肩に掛けてきた。
「そうだな、大分制約はあるが……会いたい人などいるだろうか?」
「会いたい……人……」
「おまえが生きていると知っている者に限るが」
意地の悪い問いだと思った。わたしが生きていることを知っている者など伊勢の尼君くらいだ。交友関係を無視して広げるならあの脱出劇の時にわたしを逃がした大坂方の忍び、さらに考えるならわたしを処刑したとして隠蔽した者たち――
「それでは……伊達の軍師殿にお会いしたい」
「竜の右目に? それ程親交があったのか?」
「いいえ、東軍でどれだけの人が知ってるかわからないし、知ってるだろう軍師ってその位しか思いつかないの」
「確かに彼なら知っているが」
「昔語りをしたいの。そういえばあの時伊達殿を引き合いに出して随分怒りを買ったわね」
「分かった。伊達軍なら丁度駿府に寄る予定がある。その時に場を設けよう」
再度、養生するようにとの言葉を残して家康は戻っていった。小さなため息と共に日を背負う彼の後ろ姿を見送って脇息にぐったりと凭れたが誰もそのはしたなさを責めることはない。
知っている者の消去法ではあったが敢えて伊達の軍師を名指しする程でもなかった気がする。何故その名を出したのか。竜の右目がどうこうしてくれるわけでもないだろうに。ただ人が恋しかったのかもしれない。どんどん只人となっていく自分がいる。所詮、師に憧れるだけの人生であったのだろうか。
「詮無いことね……」
そのまま脇息に伏せれば腹に鈍痛を感じる。身籠もるとよく起こるそうだ。腹の者が確かにここに居るのだと布達するかのようで薄ら寒い。
嗚呼、何故この身は女であったのか。