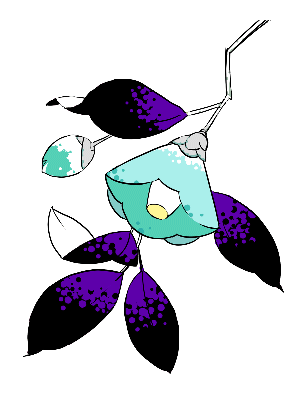
それから一月ばかり経った。米蔵襲撃の打撃が響いたのか、出陣には至っていない。それでも城には様々な人と物が出入りしているようで出陣は秒読みなのだろう。
わたしの動きを警戒してか、あの日以来二の丸の近くには本多忠勝が詰め、わたしの動向は常に家康に筒抜けである。戦国最強と謂われる男を前にしては逃げ道など完全に絶たれたと言っていい。尤も、あのような出来事がまた起こるなどあり得ないことであるが。
「二の丸様、日が陰って冷えて参ります。お膝に一枚掛けられますか?」
そう言って近寄ってきたのは白粉の香りの少しきつい侍女の一人だ。
本多忠勝がここに詰めていることが安堵に繋がったのか、くノ一の数よりも侍女の数が増えた。彼女たちはわたしが鴨跖草の軍師であることをむろん承知しており、二の丸御殿をもっと美しく、もっと華美にと言わんばかりにあれこれ用意してくる。まるで、軍師であるわたしと二の丸殿を完全に剥離させようとするかの如くで気味が悪い。
「いらないわ」
「そう仰いますな。御身大事にして頂かねばなりませぬ」
続く文言は分かっている。貴女様は家康様の御側室なのですから、あたりだろう。立ち上がって広縁を行き格子に手を掛ける。姿は見えねども動く気配が姦しい。
「出陣はいつなのかしらね。これ以上遅くなれば兵は皆凍えてしまうでしょうに。そういう衣は外で動く者たちにあればいいのよ」
「お優しい御心なれど、その者らよりも二の丸様の御身の方が大事にございまする」
「変なことを言うのね。家康が怒るわよ。あの人は一兵までも大切にする人だから」
侍女は、まあ、と言って顔を赤くする。その認識は正しい。わたしの皮肉だ。
そうだ、家康は苦楽を共にした家臣たちを骨の髄まで信頼し大切にしてきた。なのにこのたびは出陣を伸ばし、冬に至ろうかというところまで来ている。このままでは極寒の中で兵を戦わせることになると分からない男ではないはずなのだが。
「まあ、戦人の家康なんて関ヶ原までしか知らないし、天下を取って変わったのかしらね」
人は変わるのだ。だからこそ変わりたくないと、瞼の奥に棲む師を追うわたしを皆は歯がゆく思うのだろう。誰かと一緒でなければ排斥されるのか、理不尽な話だ。
「二の丸様……」
「なに?」
「二の丸様はいつも、皮肉を言われた後は苦しそうなお顔をなさいます」
「え?」
「どうかその、わたくしは戦場に出ぬ者でございますけども、二の丸様は肩の荷を降ろされてもよいのではと思うことがございます」
「……変なことを言うのね。わたしは重荷と思ったことなんてないわ。あの方の傍で学び采配を奮い忠義を尽くす、これほどの誉れはなかったもの。重荷というのは、ここの皆の期待のことよ」
白粉の香りのする侍女は遠慮がちに首を振りなおも続けた。
「なれどもやはりおなごの喜びは愛し愛されることと存じまする。二の丸様は皆が望んでも得られぬ方の愛を得ておられます。家康様は貴女様以外のおなごを悉く拒んでおいでです。貴女様には家康様の御子を是非に是非に生んで頂きたいのです」
「本当に変なことを言うわ。それは次の重荷を背負えということでしょう」
「それでも、未来ある荷でございます」
「未来、ね……」
豊臣の栄光は完全に過去へと置き去りにされている。主要な者が死した今戻ることは難しい。だから何度でも思うのだ。それならばわたしもそこへ身を躍らせたいと。
「わたしに乞うより家康に言った方がいいと思うわ。違うわね、貴方たちは何度もそう進言したでしょうね」
侍女の返答はあえて聞かなかった。どうせ何度も繰り返された堂々巡りが続くだけだ。
斜陽は進み、格子に間延びした影を作る。もう逢魔が時か、この影の先にわたしを連れて行く者らが現れてくれるならどんなにいいだろうか。
そう思いながら影の先を目で追った。その先にたどり着く前に侍女が、あ、とか細く声を上げ深々と頭を垂れる。
「本多様」
わたしにはない敬意を向けられた、大きな躯体に枯茶の具足を纏う武士――本多忠勝がそこに立っていた。家康に過ぎたる者と他家の者に言わしめる彼は様々な賛辞が付きまとう。戦国最強と謳われる武勲、そして家康を守り抜き天下人となるまで引き上げた忠義者。家康には様々な家臣がいるが、家康の心を尤も理解しているのはこの忠勝だろう。考えてみれば、彼があの時わたしを殺してくれていたのなら今頃こんな苦しみはなかったと思えば殊更愛想を振りまいてやることもない。
「なにか?」
「――!」
この御仁は不思議である。口を開いてもいないのに彼が何を言いたいのかが分かる。声が聞こえない代わりにキュイーンと風変わりな具足の音がする。一時期、これは何かしらの術なのかと真剣に議論が繰り返されたくらいだ。
”様、少しお話がしたいのです”
「わたしは貴方に文句しかありませんよ」
”お許しを”
「本多殿におかれましてはどのようなお話があるのでしょう。また内府殿を受け入れろとのお話ならば仰るだけ無駄です。そういえば本多殿とはそのようなお話をしたことはありませんでしたね」
”はい、左様です”
「……お客様のお席を用意して」
「心得ましてございます」
此処に押し込められてからというもの本当に駄々のみになったしまった気がしてばつが悪い。本多忠勝という人は昔からあまり語ることのない男で、わたしとしては徳川四天王と呼ばれる者らの中でこの男が一番苦手であった。家康などは心優しく頼りになると言ったがわたしからすれば御しにくいの一言に尽きる。血気盛んな井伊直政は怒らせればよかったし、酒井忠次は年長者であることをつつけばよかった。知恵者の榊原康政とは似た者同士、腹の探り合いをすればどうにかなる。
彼は無口で献身的で強い。味方であればそれでいいのだが格段落ち度がない人間は蹴落とすことが難しい。そう、忠勝は面倒くさいのだ。
その強さから手を出すことをしなかったが今思えば自分が軍師のうちに真っ先に潰しておけばよかった人物だろう。
席はすぐに整えられて温かい茶が振るまわれる。大きな躯体が正座する姿は部屋に似合わないのは相変わらずだ。揺蕩う湯気が消えぬうちにと一手踏み出すことにした。
「それで如何なさいました?」
”まずはこちらを……”
彼がそう言った気がしたと同時に忠勝がもぞもぞと動き出した。するとチリンと音がして彼の首の下あたりから小さな客人が顔を出してきた。そうあの鈴の子猫だ。一月も経てば子猫は成長し顔はほんの少し精悍になっている。
「まあ、どこに入れておいでなのです」
”最初は手に抱いていたのですが入り込みました”
「この子にかかれば戦国最強も形無しですね」
傍に仕舞っていた玩具を取り出して放ってやれば子猫は吸い寄せられるように遊び出す。一月前よりは動きは機敏で玩具もすぐに壊してしまいそうだ。
”あれよりお傍に置いていらっしゃらないようなので連れて参りました”
「元々わたしのものではないし、格子の中だけで遊ぶこともないでしょうから。わたしに付き合わせることもないでしょう」
”左様お考えでしたか。……貴女様がある一点だけ御承服下さるなら外へも行けましょうに”
「それは無理でしょうね」
”仰ぐ旗は変えられぬ、ということですね”
「ええ。……家康の辛抱強さには関心します。わたしが雑賀や井伊の女地頭のように武を持って制する身なら今頃墓の中に居れましたでしょう。本当に、軍師とは何だったのでしょうね」
もう少し時があればわたしにも大きな領地があったかもしれないし半兵衛さま側近で太閤陪臣でなかったかもしれない。そういえばあの伊達の右目殿はすでに多くの領地を得ていた気がする。
”貴女様も頑固であられます。しかしほんの少しでも心お弱くなられる時がありますなら、我が主君に心を預けられても良いと思います。一時の迷いでも。”
「あら、本多殿からそのような誘惑を頂戴するとは」
袖で口許を隠して笑うわたしは最早ただの女子なのかもしれない。果たして徳川四天王の中でどれだけの人間がわたしを警戒しているかといえば微妙なところだろう。足掻くわたしは手足を取られた道化に近い。
「家康が誠実な人だということは重々承知しています」
”では何故。竹中様は主君よりも誠実なお人柄だったのでしょうか”
「誠実、そんなのはわかりません。ただわたしにとってはこの世の総てでありました。何よりも大切でそれは不変です。何度も言っているのに徳川の人たちはどうして分かってくれないのかしら?」
困ったように笑って見せると忠勝の戸惑いを感じる。豊臣でわたしたちが心安く話す姿を彼はずっと見ていた。彼の心中とて複雑なものであるのは想像に難くない。だからこそ彼に言わなければならないことは多々ある。
「本多殿、わたしはいつ殺されてもかまいません。近い将来わたしが家康を受け入れずいつまでも世継ぎが出来ないとなれば二の丸殿の排斥を目論む者が出るでしょう。家康の怒りを買ってでもそうしなければならないと思う忠義者が三河者にはいるはずです。その時は、いえその時こそは貴方がわたしを殺してください」
”様”
「そうしても罰は当たりませんよ」
だめ押しの言葉に彼が露骨に怯んだのを感じた。心苦しく何より逃げたいのはわたしだ。略奪者の側の人間がそんな態度なのは反則だと思う。これからどうなるのか思うだけで胸の苦しい日々を想像はついても思いやることは出来まい。彼らはやはり不快で相容れぬものなのだ。
なんて気持ちの悪い。本当に眩暈のするほど。
”様……?”
「ごめんなさい。……ひどく、気分が悪くなってきました。横に、なりたいのです」
嘘ではない。本当に喉から下のあたりが抉られるように気持ちが悪い。視界がぶれ倦怠感が襲い来る。
「二の丸様っ! 如何なさいました! 二の丸様っ!!」
口を袖で隠そうとしても手が持ち上がらずぐらりと上半身が揺れる。侍女と本多忠勝が慌てて支えに来る。ああ、とうとう身体まで言うことを聞かなくなるのかと思うと殊更情けなくて無駄な生を貪る我が身が口惜しく総てが暗転していくのだ。