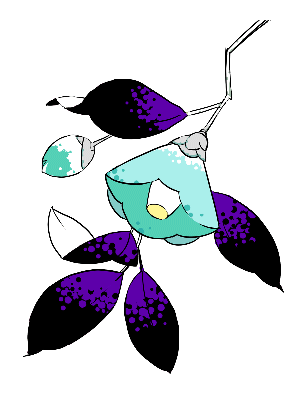
あれは十五、六の頃だったか。大した禄もなく師に付いて居た頃、幾つかの戦をこなしやっと周囲に覚えられた時のこと。愚かにも竹中半兵衛に弱点が出来たと思い込んだも者らが、次々に縁談を申し込んできた。兵法に明るい娘がいれば安心して城をあけられるだの、竹中様と縁続きになればこれほどありがたいことはないだの、その辺の娘と変わらぬ扱いだった。師の歯牙にも掛けず断る背を見ながら、女子が身を立てるというのは粋がっても仕方がないのだと、周りの評価を変えるしかないのだと思い知らされた。と同時に、門地がなくとも伊達の竜の右目のように男に生まれておればそのような煩わしさもなかったであろうと諦観したのを覚えている。
――ああでも、わたしはやはり女であったのだ。
いつの間にか灯明皿に灯った明かりを眺めながら唇は震える。とても悲しかったのだ。所詮家康にもそのようにしか想われていなかった事実が。家康の好意はおそらく真心だったろう。その家康にさえ過分な忠義は邪なものにしか映っていなかった。そんな家康に泣きじゃくって、最後まで拒めず結局はこの有様。あれは家康が手籠めにしたのではない、ただわたしが弱く縋ったのだ。
よろよろと身を起こし身形をみればちゃんと白小袖を着ていて、夢であればいいと思ったが全身にある痛みがそうでないと現実を突きつけてくる。
もうだめだ、とうとう一線を越えてしまった。せめてこれが表沙汰になる前に消えてしまいたい。僅かに残る矜持が舌を噛み切ろうとする。これで終わってくれと思いながら歯を立てたが、それは予想外の感触に感触に阻まれてしまう。
「だめだ。絶対に死なせない」
それはすぐ傍で横になっていた家康の手、彼はずっと起きていたらしく彼もまた辛そうな表情でわたしを見る。そんな顔をするくらいなら捨て置けばいいのに。貴方には寄り添って花のように微笑む女性が似合うだろうに。そんな人がきっと貴方の心を埋めてくれるだろうに。
情けなくて泪が止まらない。此処は牢獄だ。わたしの心を挫いてしまう、なんて恐ろしい場所なんだろう。
家康は徐に襖の側の方を指さした。この部屋では見覚えのない、しかし過去に確かに手にしていた物が鎮座していた。
「、見て。あの時の唐傘、もうこんなにぼろぼろになってしまった。おまえのあんな笑顔はもうみれないんだろうな」
「ずっと持っていたの」
「関ヶ原の後、一度大坂に行ったからな」
それは和睦交渉の時、わたしはその後すぐに西軍の将の一人として捕らえられ部屋のものを持ち出すことも出来なかった。あれ以来大坂城に戻ることも叶わず唐傘がどうなったかなど知る由もなかった。彼の手にあるのは思いも寄らなかったが。
「そうしたのは……貴方でしょう」
「そうだな」
それきり言葉を交わすことはなく夜が明けわたしは侍女らに手渡された。誰も言葉はない。あるのはただ重苦しい空気と昨日とは違う同情の視線だ。そんな哀れみの目を向けるくらいならはじめから逃がしてくれればいいものを。
昨日と同じように湯に浸かる。連日このようなたっぷりの湯を使えるなど贅沢なことだ。身体に付いた新しい傷より腕にある古傷に視線が行った。もう随分前だ、半兵衛さまに手合わせをして頂いたが、ある一手を避けきれず怪我を負ってしまった。元々半兵衛さまは婆娑羅者、御力にかなう訳もなく結局一本も取れずに終わった。お匙にこの傷は一生残ると言われ、己の力不足を恥じていたら、女の子の身体に傷を付けてしまったと師は眉を下げていたのを思い出す。
「半兵衛さま、ごめんなさい。あれ程目をかけて頂いたのに……」
氷のような軍師の中には何より強い意志と炎があった。そんな人に師事し身を立てて貰った。結局自分はなにも返せず家康の手の中に堕ちてしまった。
けれど、家康に付けられた傷はすぐ消える。半兵衛さまの傷は残る。そうでなければいけない。大丈夫、わたしはまだ大丈夫。
わたしの心内を聞いた者がいたら、哀れな虚勢と思うのだろう。ああそれでも、それでもわたしは曲げることは出来ない。無駄だと笑われても、愚かと泣かれても。
首を上げ湯煙を眺めれば何処か遠くへ上ってゆく。文字通り水を差すように滴が天井から伝ってくる。最近はこんなものを見る余裕すら無かったことを思い出し息を吐く。分かっている、もう自分は戻れないことくらい。
「流石に今日は一人にしてくれないか」
そう言って自室に引っ込んで何刻経ったか。近待が気を利かせて持ってきた酒も煽ることなく、頭を掻いては首を振り、ため息を吐き、そんな時間を繰り返している。
抱いた彼女は細く愛らしくいじらしかった。絡め捕った柳髪の美しさも少しだけ漂う香の香りも総てが芳しい。彼女を散々傷つけたのにどうかしている。こんな境遇に追いやっているのは自分なのに、自分のせいであそこまで身の潔白を貫こうとしているのに、あの苦悩を知ってなお離れがたい。恋とはなんと身勝手なのか。
をこの手に抱けたのは彼女の心を自分が痛めつけたからにすぎない。これからもっと拒絶されるだろうし心を開くことはないだろう。だがあの言葉だけは真摯に謝罪し続けたい。許してくれなくてもいい。彼女が自分より先に竹中半兵衛に出会ってしまったときからこれは変わらないだろうから。
「ハハッ、皆に心配されたのにワシはこうなんだな」
ただ一度の恋、その響きは筆舌に尽くしがたい。
空を眺めて暫くするとカタリと音がする。まだ本調子ではないな、と感じながら少しばかり居住まいを正す。
「家康様、半蔵めにございます」
「どうした?」
「大阪方の牢人増すばかり。各街道、また城の平野口に郭を設けているとのこと」
「時間稼ぎが必要故米蔵を燃やした、ということか」
無論、米が足りずとも出陣出来ない訳ではない。ましてあの程度の量なら参陣する大名からの寄進や道々の商家などから買えばどうにかなる。言うなればこれは挑発といった意味合いが強いのかもしれない。
「あの忍びのやりそうなことにございます」
「まあ、真田は確実に大坂に入ったということだな」
「御意」
「なあ半蔵」
「は」
「は内通していたと思うか?」
「無理でございましょう。あの時攪乱され二の丸様の傍を離れた我らに言えたことではございませんが、平素の二の丸様は誰ともやりとりの出来る環境にありませんでした。ご本人が仰るとおり偶然でありましょう。二の丸様の知謀は喉から手が出る程欲しいもの。もし、内通しておられたらあの忍び、猿飛佐助が必ず大坂に連れて帰っております。あのようにお一人で抜け出されるなどまずありえません。本多様もそのようにお考えでした」
「だろうな。いや、すまない。確信が欲しかったんだ。二人がそう言ってくれるならそうなのだろう」
「とはいえ、二の丸様が鴨跖草殿だと大坂に露見してしまったことには変わりありません。御身辺には更なる用心が必要となりましょう」
「そうだな」
よりによって一番厄介な者にばれてしまった。ワシとの巡り合わせはとことん悪いと言わざるを得ない。ワシの機微を感じ取ったらしい半蔵の瞼が僅かに動く。
「その件につきましては差し当たり本多様が二の丸御殿の近くに控えておられます。本多様がおられるとなれば猿飛も容易に接触は出来ますまい」
「二人共よく気がつくなぁ。助かるよ。だが半蔵、傷はまだ塞がっていないだろう? ちゃんと休め。出陣の折はおまえがいなければ話にならない」
「ありがたく」
そう言って平伏した後、彼は先程より音を消して消えていった。
半蔵が消えて暫くすると一陣風が吹いて、甘い香りが鼻を掠める。それは我が身についた彼の人の残りがだろうか。