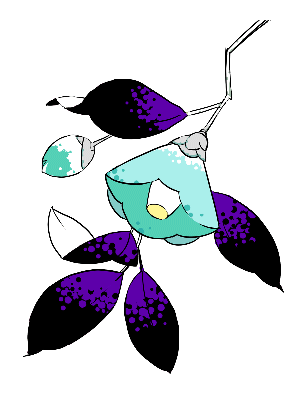
大きな失望と悔しさだけが心を包んでいく。死した者は皆過去なのだと、眩しい東照は言い放ったのだ。わたしまで忘れてしまったら誰がその無念を伝える。誰がその意志を繋ぐというのか。
ああ、これが敗者であるわたしと勝者である家康との違いだ。負けぬ為の戦いを学んだはずなのに、わたしは三成の助けにもならなかった。師はなんの為にわたしに兵法を叩き込んでくれたのだ。それなのに二人は泉下の人となり何故わたしだけが息を吸っているのか。
「三、成、……半兵衛さまっ……」
噛んだ口から漏れたのはやはりその名だった。その刹那、わたしの拳は大きな拳に掴まれ苦々しげな声が降る。
「おまえの眸には、豊臣しか、いや、竹中半兵衛しか映らないのかっ……。おまえなら望めばどんなところでも嫁げたはずだ。だが長年嫁がなかったのはっ」
『半兵衛殿を愛していたからなのか?』
瞬間、何かが瓦解する音がした。
「……結局、貴方もそうなのね」
沸点に達して、一気に氷点下まで落ちるというのはこういう感覚なのかと思う。わたしは家康の手を振り払って立ち上がり、衝動的に部屋の外へ出ようと足が向く。皆が居ようが先に格子があろがそんなことは構わない。しかし当然のように畏まって制するのは榊原康政だ。
「二の丸様! どうぞお待ちになって家康様の話をお聞き下さいっ」
「二の丸様? 榊原殿、わたしはそのような名ではない。貴方はわたしをなんと呼んでいた! わたしは豊臣の臣で貴方は徳川の臣、貴方に頭を下げられる謂われもなければ上に立ったこともない!」
暫しわたしを指す”鴨跖草の軍師殿”を名付けたのは他ならぬ康政だ。よく鴨頭草の色目の衣裳を身につけていたから、と彼は言ったが、鴨頭草とは移り気な男をなじる表現にも使われるのを思い出し鼻白んだのを覚えている。まあ和歌などあまり詠まないだろうからね、と師も苦笑してそのままにしていたのだが。
「なれども貴女様は――」
「!」
追い縋る家康の手をもう一度払って、今はもう激情だけが先走るわたしは声を張り上げる。
「わたしは、半兵衛さまに邪な想いを抱いたこともなければそんな扱いをされたこともない! 父母に早くに死なれ叔父に家督が行き、屋敷の角で小さくなって過ごして、女だてらにと兵法を学ぶことも笑われた娘を拾ってちゃんと評価して下さった師を父とも兄とも慕うのは可笑しいこと!? あの方だって、もっと学べ、もっと視野を広げろ、時には厳しく、出来なければ一緒に考えて下さった、そんな方よ!」
感情とはこうも止めどなくあふれ出るものなのか、言葉と共に先程まで見えていた困惑した康政の顔も苦渋に染まる家康の顔も段々とぼやけてくる。
「わたしの人生の始まりを下さったのは半兵衛さま、ただそれだけで忠義を尽くすのは可笑しいこと? その方が残したものを護っていこうとするのは可笑しいこと? 家康貴方は、貴方ですら、という女は色香で半兵衛さまの横に居たと思っていたのっ……」
「、っ……」
「いいえ違う、徳川家康ほどの男の目にさえ、わたしはそうとしか映らなかっ……たっ……」
いつも努力した。三成が身体をぼろぼろにするくらい鍛錬に励み秀吉さまに身を尽くすなら、わたしは時間を忘れて学んだ。熱が出ようが、戦帰りで身体が動かなくなろうが、書冊は手放さず忍びからの報告も漏らさず聞き頭を回した。そんなわたしを半兵衛さまも秀吉さまも、刑部や左近も認めてくれていた。でも少し外に出ると口さがない評価はあって随分悔しい想いをしたのを覚えている。そんな評価を家康の口から聞くとは、否、家康に言われることが此処まで苦しいのか。
最後はもう嗚咽にしかならなかった。たがが外れたように身体の力が抜けて伏して大の大人が声を上げて泣きじゃくった。半兵衛さまも三成も秀吉さまも左近も刑部もいない寂しさ、心苦しさ、全部仕舞い込んで拒絶し、大坂で戦おうとした。そんなわたしの心は所詮ただの傾慕と思われていたに過ぎなかったのだ。すまなかったと失言を詫びる家康の聲も、おろおろする侍女たちや家康の近待もどうでもよかった。だた一言、みんなどこか行って、と呟くのが精一杯だった。
徐々に跫音が遠のいていく。視界に入るのはあの頃より細くなった指と美しい打掛だ。こんなものを着ているからわたしはただの女なのだと脱ぎ畳に叩きつけた。物に当たる姿は何とも情けなく滑稽で矮小な人間だと思い知らされる。
「ああっ……」
あんな評価はいつでもされていた。そんなものだと諦観していたはずだったのに。
外の雨と呼応するように涙は止めどなく溢れ頬を濡らす。流れる雨水のようにわたしも泥にまみれてそのまま何処かへ消えて終えばいいのに。
”なんてことを言ってしまったんだ”
頭の中に浮かぶ言葉はそれだけだった。
康政や近待がなにか言っていたが、自分の跫音と雨音しか耳に入らず喉は不自然に乾いて汗が噴き出してくる。
彼女は努力の人だ。振られた仕事は絶対にやり遂げたし、受け答えは明朗で彼女の指示が分からなかったこともない。鴨頭草殿は豊臣になくてはならない存在で、自分も何度も助けられた。確かに竹中半兵衛には盲信的だったが男女の仲になるような雰囲気は一度とてなかった。ある日、何日か二人が部屋に籠もって難しい仕事をしていたときがあった。左近が三成と自分を連れて覗きに行くと、髪をぼさぼさにしたがうんうん唸りながら地図を睨め付け、半兵衛殿は力尽きたように顔に文書を乗せて寝ている姿を目にした。あまりの色気のなさに左近がどん引きし、三成がまたか、と言いたげにの頭を叩いて、寝ろ、と部屋に引きずって行っていたではないか。ワシは見ていたではないか。あの二人がそんな関係でないことを。
「非道い失言だ。醜い嫉妬で完膚なきまでに傷つけてしまった」
「家康様……」
「見ていたはずなのにな」
本丸へ戻る足が重い。あれほど地に足をつけて生きていた女性を奪って、傷つけて、泣かせて、そして今逃げ帰っている。自分が望んだことはこんなことではないはずだ。豊臣を裏切ると決めたときから反目するのは分かっていたこと。それでも愛した、詰られても嫌われてもいずれまた彼女が微笑んでくれたらと。
歩みをとめたワシを近待が怪訝そうに様子を伺ってくる。
「のところへ戻る。誰も二の丸殿に近づくな」
あ、と侍女等の声がした。幾人かは止めようとしたのかもしれないがたとえそうされても今は振り払っただろう。早足で戻れば打掛を脱ぎ捨て打ちひしがれる愛しい人の姿。こんなにもか細かっただろうか。たまらず後ろから抱いてみれば返ってくるのはやはり弱々しい拒絶だった。
「、、すまなかった」
「帰って」
「嫌だ! 今帰ったら一生後悔する!」
「帰って。わたしは裏切る訳にはいかないの」
軍師として終わりたいと彼女は言った。自分の中には忠義しかないのに皆がそう思うから、半兵衛殿の名誉も自分の名誉もこの身で立てるしかないのだと。
「だからおまえは頑なにワシを拒んだか」
意固地ではなかった。一人で耐えるひたすらに健気な女だったのか、身につまされる思いが駆け抜けて今度は胸に掻き抱いた。たまらなく愛おしくて額に口付けたら、瞼を震わせながら、嫌、と拒絶してくる。彼女の心は一生自分の物にはならない。ああ、の細腕がワシの胸を押して逃げようとする。その腕を奪って今度は唇を吸えば、身を捩って頬は涙に濡れた。
彼女の抵抗など本当に取るに足らないもので。こんな身で戦場に出ていたというのだから自分がどれ程の温床にいたか分からないだろう。横抱きにして奥へ進めば佳人はいよいよ悲鳴を上げて、嫌、放して、と泣いて拳をぶつけてくるが些細なものだった。
褥に散らばる彼女の髪は美しく、高価な小袖は完全な飾り物だ。帯が舞い、それでも逃れようとするが憎らしくも愛おしい。嫌だ嫌だと泣く彼女の耳に何度も囁いた。
「そうだ、ワシが勝手に抱いてるんだ。おまえは拒んだがどうにもならなかったんだ」
それでもは抵抗を続け忠節を保とうとする。早く諦めてワシのせいだと詰ればいいものを。
拒絶の言葉を並べる薄紅の唇が家康、家康、と紡ぎだして爪を立てていた指が空を掴むようになる頃、雨は止んでいた。