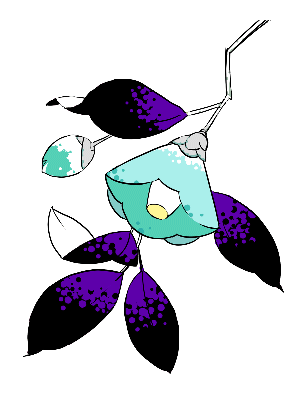
少し前まで何かの花の香りがしたと思っていたのに、いつの間にか鼻孔を掠めるのは独特な湿気の香り、そうして耳を撫でたのはザァーという小さな水滴が無数に跳ねる音、ああ、雨か。近々雨が降ると尼君が言っていたっけ。早く支度をしなくては――。
「――ぃ、っ……」
無意識に身動ぎすれば項(うなじ)に激痛が走って呻き声が漏れる。すると少し距離のある場所から、二の丸様お目覚めにございますか? との声が聞こえたがわたしは答えなかった。
動けないから見つめる格天井には見覚えのある花々が描かれていてはっきりしない脳が、いつぞやを繰り返して永遠に抜け出せないのではないか? という錯覚を引っ張り出してくる。
否、そうではない。聞こえた声はわたしをさまではなく二の丸様、と呼んでいたから、ただ単純に死ぬことも叶わず連れ戻されただけだろう。だけ、というのも随分肝の座った話であるけども。
「また死ねなかったか」
此度ばかりは誰も答えなかった。それはそうだろうと思う。何度言っても頑なな二の丸殿、城が燃えるという混乱に乗じて抜け出して、多分何人か怪我もしたろうし、警護の任の者は処罰もされただろう。その上言うに事欠いて、また死ねなかった、では。気付けば自分でも驚くくらいの乾いた笑い声が出る。
振り出しなどというものではない。これからよくて座敷牢、悪ければ怪しげな薬でも飲まされて家康の前に出されるか、そんなとこだ。それを口にすれば、家康様はそんなことはなさいません! と口惜しげに返されるだけだろうが。皆このわたしが口惜しいと思うなら本当にその懐の匕首で突き刺してしまえばいいものを。
彼女らの所作は淡々と続いて、お首やおみ足の加減は如何でございますか?、お手水でございます、御衣裳はこちらにございますが、お湯殿の用意もできております、お膳が先でもかまいません、と一見甲斐甲斐しいが事務的にも見えた。放って置いて欲しいがこうされる方が楽だ。ようやく誰もわたしの心に入ろうとはしなくなったのだ。
「全部済ますわ、湯に浸かった後に身支度を。それから少し食べます。足は痛むから軟膏を。あと首が動かないの。どなたか手を貸してくださる?」
拒否されると踏んでいたのか、ざわつきがみえたがこちらが乗ってやる必要もないのでもう一度、手貸して、と催促してやった。どうせわたしが目を覚ましたと連絡が行くのだ。少しでも身形を整え力を付け、あわよくば一矢報いてやらねば。わたしに残った豊臣の者としての矜持だ。女としてはただただ恐ろしいばかりだけれど。
何刻程経ったか。きっと相手を待たせているであろうに念入りに洗った髪が乾く程度には過ぎている。目を覚ましたのは朝方であったらしくあのときよりは若干空も暗い。
先程までわたしの髪を仰いでいた侍女が、麦湯を用意致します、と辞していった。この雨の日に女主人の髪を乾かす羽目になるとは本当にご苦労なことだ。ここの侍女達はいつ起きるとも何をするとも分からぬ女の為に全てを用意して待っているのだ。これを徒消と言わずしてなんというのか。
「今、何刻ですか?」
「申の刻も半分はすぎておりますかと」
「そう」
であれば大方の執務は終わり家臣たちと雑談でもしているところか。
「ひどい雨だこと」
このような雨ならどんな策が練れるか思案した日々は遠い。忌々しい雨から遠ざかろうと書院を眺めれば以前のままの書冊が並ぶ。此処に道ならぬ恋のものがたりでも並べば何の冗談だと笑ってやるものを。
一冊、兵法書を手に取った。懐かしい師の教え、この兵法の矛盾点を答えよとの課題に、本の紙が千切れ紐が緩む程何度も読んで答えに到達するのに要した日数は二十日。もう呆れられているかと恐る恐る答えたら、優しく微笑んで下さって、よく出来たね。実は三成君は倍の日数が懸かったんだよ、と仰った。三成と比較されたことよりもあの方がちゃんと評価して下さったことが嬉しかった。あの時あの場に居た者はもう居ないから、これはわたしだけの大切な思い出だ。この本を抱きしめることを怪訝に思われたとて誰にも教えてやるものか。
――リ……チリ……、……ン……
暫しの郷愁から現実に引き戻すのは鈴の音だ。少しばかり首を動かせば小さくて丸いあの子が侍女らに咎められること無く入ってきて几帳の裾と戯れていた。
「まあ、あなた、此処に来てくれたの?」
真白の小さな仔猫に屈んで手を差し出せばよたよたとしながらも擦り寄ってくる。あなたを置いていった人間だというのに、無垢なものに晒される我が身のなんと醜いことか。
僅かに瞼が震えるのを感じながら仔猫を抱いて立ち上がると障子の先に影が揺らめいて見えた。侍女らはすでに平伏しており誰がいるかなど一目瞭然、平素ならば一声あってわたしが逃げ出して終いなのだが。
「」
「……家康」
どこか神妙な家康の聲を聞きながら、ああ、侍女と溝が出来るとこういう弊害もあったか、と諦観した。そのくせ傍目にも分かるくらい身が縮み上がるのだから滑稽だ。
「今日は、少し話そう」
「話すことなどないわ」
「そう言うな。ワシも避けられて終いにしていたから、それではだめだろう」
障子の先には家康付きの近習の他に榊原康政の姿まであって容易ならざる空気が流れて、わたしの沈黙を了承と取った侍女が茵やら場を整えていく。我が身を守るように猫を抱き家康と向かいに座らされ生きている心地がしない。皆が固唾を飲む重苦しい沈黙の後、口火を切ったのは家康だった。
「なんというか、おまえには驚かされたよ。大坂方の忍びといつ連絡なんて取れたんだ?」
「忍び? そんなものといつ示し合わせが出来るというの? わたしの周りには貴方の息がかかった者ばかりなのに? あれは本当に偶然。侍女が慌てふためいていたから外を覗いたの。そしたら城が燃えていて、今しかないと思った。もう一度大坂に……、それが叶わぬなら……」
「叶わぬなら?」
「いいえ、本当に埒もないこと。貴方に感化されてつまらないことを考えただけ、忘れて」
すると家康が格天井を仰ぎ見て感情を霧散するように大きく息を吐いた。
「、ワシは軍師としてのおまえも見てきたし、だからこそずっと待った。当然敵対したのだから苦々しいと思う。だがおまえにとってワシは今でも取るに足らない男だろうか」
「……わたしが三河の生まれで、もっと早くに貴方に会っていたら、わたしはきっと貴方の背中を護って、時には押していたでしょうね。貴方はとても立派な将で君主だわ。けど、それを言っても」
「ああ、何にもならない。ワシは三河で生まれ、おまえは美濃で生まれた」
「そうね」
場の空気は鉛のように重苦しく、家康も何処か行き場のない感情を持て余すようだった。そんな家康を見るのは初めてで彼にもそういう感情があるのかと身も蓋もない考えが過ぎる。
「おまえに言わなければならないことがある。先日征夷大将軍の宣旨を受けた。だが豊臣は受け入れるわけもない。恭順してくれたなら道もあったが、あちらは一戦交える気しかなく全国に檄文を飛ばす始末。徳川としては滅ぼすしか道はない」
「勝手ね。秀吉様を屠り、三成を殺し、その先が征夷大将軍? 当たり前だわ。豊臣からすれば簒奪だもの」
「ああそうだ。簒奪と言われても、日ノ本を世界から護るためには豊臣の支配する世は享受出来ない。おまえなら豊臣の愚かしさもまた分かっていたはずだ」
「それでもよ。受けたご恩は返すの」
「、豊臣の檄文に応えたのは改易になった者や牢人だけだ。――竹中家も我らに付いた」
「なんですって」
半兵衛さまが身罷る際、わたしは竹中の養女となったが、血縁がある訳でもないし、本家分家に縛られず動けるようにとの半兵衛さまの配慮から別家扱いだった。関ヶ原の折、わたしの竹中家は断絶で一代限りとなったが、半兵衛さまゆかりの竹中家は続いていた。その家があっさりと豊臣を見限ったのだという。大した能力もなかったが甘い汁を吸おうとしては半兵衛さまや三成に咎められていただけの者らだった。恩義など彼らの脳裏には無かったのだろう。
「痴れ者共……っ、半兵衛さまの、竹中の者でありながらっ」
「竹中本家が裏切った今、たとえおまえが忠節を持って戻ったとしても、内通者として警戒されるか処断されるかが関の山だ」
なんて残酷な言葉を吐く口なのだろう。脳裏を過ぎるのは次々と離反され、闇へと沈んでゆく僚友の顔だ。嗚呼三成、貴方もこんな想いを抱いたか。家康のことはきっとわたしのことより信頼していただろう貴方、信頼する友に主君を殺され、離反によって手足をもがれ、この口惜しさが分かるのはわたしと貴方だけだ。わたしもあの時、開城などせず打って出れば今頃貴方と家康の悪口でも言えたであろうに。
いつの間にか手をすり抜けた猫は家康の傍で遊んでいる。家康や侍女が見ていることなど構わずわたしの手は襟先を握りしめ震えて、対して家康は憎らしいほど通る声で耳を突いてくる。
「ワシは後悔しない。秀吉公を弑したことも、三成を討ったことも。ワシの周りには絆を信じて付いてきてくれた者たちが沢山いる。間違ってるなどと、悲しくてたまらないなどと口が裂けても言えないんだ。ただ、生きているお前に対して後悔はしたくない。……出来ればワシの手を取ってはくれないか」
「……それは師であり父にも等しい半兵衛さまが作り上げた豊臣を壊した男に身体を開けということなの?」
「っ……」
「貴方は卑怯よ。高潔を笠に着て人を追い詰める。……豊臣の施策に全く落ち度がなかったとは言わないわ。その中でどれだけ民に負担がいかないか裏方のわたしたちが最善を模索していたか貴方は知らないでしょう。三成だって貴方から見れば苛烈な秀吉様の命令を実行する悪鬼にみえたでしょうね。彼はただ、秀吉様に忠実であっただけだし、彼からすれば貴方は大切な主君を大切な親友が殺したのよ」
「たとえそうでも、民を思えばそれが何にも勝る」
「そうね、そうよ。貴方は正しいわ。そうやって外堀を埋めていくの。まだ手はあったはず、あったはずなのに! 貴方はそうやって三成を弑してわたしを閉じこめるんだわ。――貴方の手を取れですって? 一途に敵の女を想う貴方を気の毒がる周囲に気遣って貴方の子を孕めとでもいうの! そんなことを言うならっ殺したのが何故貴方だったのっ……、何故貴方が立たねばならなかったの……っ」
「秀吉公のこと、何と言ってくれても構わない。ただ、おまえも三成も過去ばかりみる……それが残念だ」
過去への執着は悪なのだろうか。敗者に勝者は往々にして告げる。”過去を忘れ前を向いて生きろ。生きていれば立つ瀬もある”などと。わたしの場合は家康を受け入れろ、だ。
「わたしにとって半兵衛さまは過去ではないっ! 何も失っていない貴方にはわからない!」
なんて口惜しい。勝者というのはやはり偽善で無慈悲である。