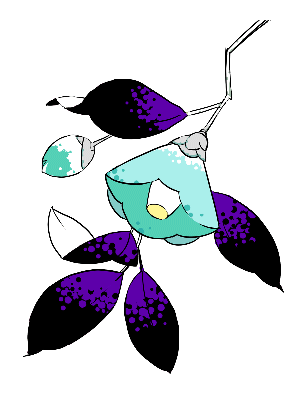
ずっと求めていた女が倒れてきた。もう最期と覚悟を決めた行動だと思えば止めることが躊躇われて、でもそれは彼女が自分を見ていないのだと再認識させられるに十分だった。
「遅くなり申した」
「半蔵」
彼女は生きている。半蔵が寸でで間に合ったのだ。家康を護る為、血迷った二の丸殿めがけて駆け寄る誰よりも早くを昏倒させたに過ぎない。はまた死ぬことが出来なかった。抱きしめた身体は細く、こんな頼りなき身で自分を拒み続けたかと思えば、いじらしくも切なく、そして苦しい。知らぬ間にハハと笑い声が出てしまう。
「こうでもしなければ、わしはおまえに触れられないのかっ……」
それだけ彼女から奪ったというのに、ああ、泣いてしまいそうだった。情けなくもその顔を皆に晒してしまって内府も天下人もあったものではない。
尼君は悟ったようだ。これは報われない恋なのだと、わしより先に尼君は泣いてしまった。
「尼君、此度は手間をかけてすまない。心配しなくていい、此処の者は皆貴女を慕っている。貴女に何かして朝廷と揉める気もない。心穏やかに過ごして欲しい」
「ああ、内府さま、この尼などどうとなさっても構いませぬ。なれど内府さまのお気持ちを知ろうとも、わたくしめは先にさまのお心内を知っておりまする。御仏に仕える身が、助けを求める力無き女子をお上に引き渡すなど出来ようはずがございません」
「……尼君、だから皆貴女を慕うのでしょうね」
自分の身とて危ないと分からない尼君ではないだろうになおも彼女は心苦しそうに懇願してくる。
「どうか暫し、この尼にお預け下さい。恩ある御家に忠義を尽くすは武門の誉れ。上も下も殺し合う昨今、それを貫こうとなさるは誉められこそすれ、非難されるものではありません。まして、竹中さまはさまにとって親にも勝る御方……」
「何を申す。そしてまた逃がされるのであろう。家康様がどのような想いで二の丸様を」
「よせ。――尼君、貴女こそ武門の出ならお分かりになられるはず。それが通らぬ世であることも」
「内府さま……。なれどお待ちになられてこそ御心を得られると存じます。そのような方を得られたときこそ貴方さまのお気持ちは真に満たされるのではありますまいか」
思わず首を振り、苦しいことを仰る、と思った。嗚呼、尼君はかつての自分のようなことを仰る。を見てもう分かっているはずだ。何年経とうがの心は変わらないことくらい。
「尼君、貴女も嘘が下手ですね」
「内府さま……」
「十分待ったと思う。死んだことにして名を奪い閉じ込めて、酷いことだろう。でも一本も触れなかった。だからこればかりは聞けないのだ」
「駿府の、二の丸御殿のご側室、とはさまであられたのですね。内府さまと同じでございまする。さまもまた戦っておられました。何年も、お一人で」
腕の中のを彼女は文字通り慈愛に満ちた顔で見ていた。菩薩が顕現するならばきっとこの尼君のような顔をされてるのだろう。
「尼にとってもさまは可愛いお人にございました。親を亡くされ、御家でのお立場が弱くなられてもなおご自分のお知恵と御心持ちで強く生きようとなさいました。言われるまま仏門に入ったわたくしには眩しく拝見するだけでどれほど心強くなりましたことか。――でも今のさまはきっと心折られお弱くなられましょう。そのような方を無理矢理お連れになられるはあまりにあまり。一時でも構いませぬ、尼にお預けくださいまし。尼のことはその後はどうそご存分にご処分ください」
「弱っている、か。ならばもうは豊臣には必要ない。そう思わないか? 尼君」
尼君はそれ以降口を噤んだ。何を言っても無駄だと思い知ったのだろう。彼女や船頭たちの処分には、何もするな、これからはああいう人材が必要だと言いおいてを横抱きにして来た道を戻る。ぼろを着ていても美しいと思う。拒絶されてもただ一層に愛おしい。酷いことをしてると思ってもどうしても諦めきれない。
「すまない、」
後ろの康政はそろそろ匙を投げるかもしれない。おまえたちにも申し訳なく思っている。諦めなくていいと言ってくれているが自分が想いを断ち切ればこんな手間もないのだ。だが口にするのは止めた。そんなことをすれば彼らもただ苦しいだけだから。
「巫殿には足止めをして申し訳なかったな。伊予までの道中、しっかりと守って差し上げてくれ」
「はっ。なれど姫巫殿のご神託とは凄いものでございましたね。以前二の丸様の命乞いをなさった御方故失せものは何かお伝えしませんでしたのに」
「巫殿は、西の方角に薄紫の雲が懸かっていたと言っていたな」
「はい、格の高いお色故あれは多分伊勢のお社の辺りだと」
「薄紫の雲、か」
話を聞いたとき、家臣等は吉兆だ、とも天が味方しているとも言った。後日本当にが居ると分かると二の丸様ご自身から神気でも出ているのでしょうかと言う者すらいた。だが自分にはあの竹中半兵衛がこれ見よがしにを護っているようにしか感じられず、あの男の嘲笑う過ぎり唇を咬むしかなかった。
憤懣を隠すように小さく息を吐き、を抱え直して小さめな御座船に足を踏み入れる。御座船と言っても徳川には華美なものはなくせいぜい関船に毛の生えた程度にしか見えない。わざわざこの船で来たのは彼女を雨ざらしにしたくないが故。彼女はきっと気にもしないだろうが。
しかしなんて皮肉だろうか。彼女が乗る船は望みとは真逆の方向へ向かうのだ。
佳人を横たえ衾をかけてやれば、身じろぎして首許が見えた。首の後ろは赤く腫れて半蔵が想像以上の力を叩き込んだことが分かる。半蔵め、と思ったがこれはが途中目を覚まして暴れることを懸念してだとも思えた。白い足先には血豆が破れた箇所もあれば擦り傷もあった。奥御殿に置いて忘れかけていたが、あの頃はしょっちゅうこんな傷を作っては軟膏を塗っていた。山や丘に登り実際に地形を見てそうして策を練って、輝いていたあの頃だ。
「ああ、くそ」
皆に気を遣わせを傷つけてなお、押し寄せるのは諦めきれない想い。この想いはきっと悪役にならねば遂げることは出来ぬ。にはさらに嫌われ巫殿には侮蔑の目を向けられるだろう。
思わないではない。軍師亡き後の太閤の行動に目を瞑り臣従していれば彼女と敵対することはなく、望めば迎えれることが出来たかもしれない。夫婦として信頼関係が出来てから離反すれば良かったのだ。――否、否だ。それは徳川の当主としても、日ノ本の民としても許容できるものではない。後少し遅かったら、日ノ本はきっと世界の争いに巻き込まれ国そのものが無くなっていたかもしれない。
太閤の傍でそれに気づいていたのは何人居たか。秀吉公に心酔する三成は無理だ。そして三成に仕えることしか考えていない左近も言うに及ばず。まず自分と、刑部もそうであったかもしれないが彼は進言することもなく終わったはずだ。結局の苦言は取り入れられず、自分は反旗を翻すしかなかったのだ。何度繰り返してもこれは変わらない。徳川家康という人間が為政者である限り。
「酷いじゃないか独眼竜、おまえの言うようにならないぞ」
生きていればやり直せる、奥州にいる盟友はかつてそう言って処断に悩むワシの背中を押した。
「なるようにしかならないか、なあ?」
柳髪を一房掬って口付けた。あまりに甘く泪が出そうになった。