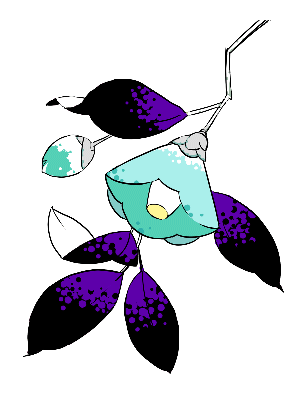
「こちらへ」
夕暮れの喧噪は尼寺を抜け出し人気のない小径を過ぎるまで続いてくれた。宿に向かう参拝者たちに逆行しながら進むさまは徳川から豊臣へ、まさに栄華の時を流れに逆らい上る魚のよう。何という魚であったか、確かその魚は成長し子を産む為に生まれ出づった故郷へ戻るのだと聞いた。ふ、笑いが出た。これが本当に家康の子を身籠もりでもして大坂へ戻るなら笑えもしないのだけれど。
「もう少しでございます。闇夜でと思われましょうが、大変に夜目の利く者らでございますのでご安心下さい。それから明後日には雨が降るようです。皆出来るだけ船を進めますが紀伊あたりで陸路を行くこともご念頭におかれませ」
「紀伊……」
大丈夫だろうか、と懸念が過ぎる。雑賀衆は確かに豊臣と手を組んだことがあるが、関ヶ原では家康に付いた。それは三成より家康がその器であると雑賀の女頭領が認めたからだ。森や夜に潜み相手を確実に仕留めるのは彼らの得意技だ。その雑賀を敵に回すのはかなりの累卵ではないだろうか。
「ご安心を。それはそれで良いこともあるのですよ。雑賀は長曾我部さまとも懇意でございます。船を早く進める事の出来る絡繰りなどがあの地にもありまして、雑賀の者以外でもいくつか扱えるのですよ。一晩身を隠し新しい船に乗り換えることも出来まする」
「そういうものがあるなら徳川が取り上げると思っていたけど……」
「そこはそれ、かつて大名の支配を受けなかった者らのしたたかさでしょうね」
「そう、……視野というのはいつでも広げなければ駄目ね」
「まこと。この尼も経をとなえるだけでは知ることも出来ませんでした」
それは式年遷宮の為に奔走した中で見つけたものだったのだろう。食うにも困る朝廷を動かし、神仏を信じぬ豊臣を説き伏せるには相当の知恵と努力を要したに違いない。刃を持たぬともこの尼君は幾多の戦場をくぐり抜けている。
ああ、見えて参りました、と尼君は言い、大きな船着き場からは少し離れた場所に漁船のような船が一艘留まっていた。
「本当なら、伊勢船をご用意しとうございましたけど夜に大きな荷を運ぶ船が動いておりましたら目立ちますゆえ……。近くの船頭たちは皆酒盛りでもしておりましょうから今のうちに」
「尼君、何から何までありがとうございます」
「なんの、御仏の教えのまま尼は動いておるだけにございます」
何も聞かずとも分かっているはずだ。駿府の方に異変がありそこから死んだはずの豊臣の女軍師が流れてきた。匿うだけでも天下人を敵とする。なのに彼女は手を合わせ微笑むばかり、このような慈悲をわたしは持つことは出来ないだろう。
尼君は灯火を掲げ漁船に近づいていく。さあ、と促されると思っていたその時だ。
「あ、さま! お逃げになって!」
船を覗いた瞬間聞こえたのはそんな言葉だった。
「――っ!」
想いに耽りすぎた。今はそのようなことを思う時ではなかった。目を凝らせば船の中で船頭たちが縛られ床に押しつけられていて、後悔する前に衣擦れと太刀が音を立て周囲を包んでいく。ただの物盗りであって欲しいと願えども状況は明らかに違う。物盗りならば船頭を縛り上げるなどせずとうに殺しているだろう。そうして近づく足音に睨みつければ見知った顔が現れる。
「二の丸様、どうぞそこまでに」
「――榊原康政……!」
次に顔を合わせるならば戦場で、そう思っていた男の顔だ。彼は非常に複雑そうにそして何か言いたげだったがそれ以上告げることはなかった。ただ背後で、後ろ手に縛り上げられた尼君だけが、二の丸さま? と声を上げるのみだ。
此処で終わりか。終わってなるものか。胸元の匕首、袖の下にある花ち弁、それが駄目なら喉笛に喰らいついてでもわたしは大坂に戻り太閤最後の血縁をお護りせねばならない。なのに、
「なんだ、一人か? 女一人で参れとは大坂方も存外薄情だな」
なのに、その声を聞くだけで全身から汗が噴き出るのは何故なのか。思わず後ずさりしてしまいそうなのはなんなのか。太閤に意見し、時に三成に刃を向けられても悲鳴一つ上げなかった自分がこの男を恐れている。
「家、康……」
豊臣の臣として後ろめたいことなど何一つない。怯えてはならない、怯んではならない。悪鬼羅刹のように髪を振り乱し全てを切り捨ててでも此処を越えねばならない。何一つ気取られてはならぬのだ。
頭巾に隠れた家康の表情は読めないが今、生殺与奪を握っているのはこの男だ。
「らしくないな。普段のおまえならつけられていることなどとうに気付いていただろうに」
「鈍ったということね」
皮肉なことを言う。それはそうだろう、わたしにはあの頃と違い手足として動く忍びがいない。何か察するにしても忍びの情報があればこそ。そこから策を練るのだから。
「……慶光院の尼君の遠縁といえば奥氏の娘ということになる。そんな娘の出入りが耳に入ればすぐに調べられる」
つくづく嫌な男だと思う。尼君はわたしにとって天に引き上げてくれる一本の蜘蛛の糸だというに。
わたしは眉を潜め、わざとらしく大きく息を吐いてやった。
「ふん、存外使えなかったわ。もう少しだったのに運もなかった」
「さま?」
その声に驚いたのは善良なる尼君だった。
「尼君を利用したと?」
「そうとってもらっても構わないわ。身一つで動くにはどうしても限界があるもの。陸路を走って追い剥ぎに遭ったんじゃ目も当てられない。せめて後一日船が早ければね」
家康は少し黙り込みそして頭巾を脱いで近づいてくる。睨みつけながらも一歩引いてしまうのはわたしに肝が据わらない証拠だ。
「……似合わないな、本当に、おまえは」
頭を掻きながらそう言う家康には明らかに余裕が見えてそれがまた腹立たしい。
「昔からそうだ。おまえはそういう嘘が下手だ。今だって尼君を護るためにそんな方便を言うんだろう」
「貴方は昔からおめでたいわ。わたしがなんだか忘れたの? 半兵衛さまや刑部ほどじゃないと言うならそれは彼らの影に隠れてただけに過ぎない。調略も謀略も一通りしてきたわ」
しかし彼は首を振るだけだ。
「、戻ろう」
「戻る? 何を言うの。わたしが戻る場所はっ」
「豊臣ではない!!」
「――っ」
「……今戻れば、皆不問だ。無論尼君にも一切の手出しはしない」
「まるで、悪の親玉の科白ね」
「いつの間にかそうなってしまったな」
声を張り上げるくせにどこか思い詰めたような物言いをする。何故貴方が辛い顔をするの? 何もかも、軍師としての尊厳も、命も、貴方が好きに弄んだくせに!
ああでも、もう終わりだ。このままではまたあの生活に逆戻りだ。周囲の家臣たちが絶望と共ににじり寄ってくる。知らず後ずさればすぐ後ろに尼君と尼君を捕らえる家臣がいて、わたしはずっと胸元で握っていた手を下ろして視線も下に向けた。船の側に点けられた篝火が灯りチリチリと音を立て耳を突く。
「もう、抵抗しないでくれ」
ならば――
徐々に近づく声に、何の寝言だと鼻白んだ刹那、わたしは素早く一歩下がって尼君の側にいた男の太刀を引き抜いて家康に突きつけてやった。
「さま!!」
「二の丸様!」
家康は驚きそしてその中に苦々しげな毛色が混じったのが見て取れて、このとき初めて心理的に優位になった気がした。
「嫌でしょうね。そうよ、わたしにこれを教えたのは彼だもの」
武を得ることが出来なかったわたしにほんの少し授けられたものは極々簡単なものだ。細々とした道具をまいて逃げる術、短刀で抵抗する術、そして丸腰の時相手の太刀を奪う術、関ヶ原で散ったあの無口な友の形見と言って良かった。一矢報いてやりたかった、刃届かぬまま死した友の為にも。
よせ、と家康が家臣らを制したが、わたしの刃は構わず彼の頬に傷を一つ付けた。一筋朱が滴れば、尼君の悲鳴と家臣等の激昂が一気に場を包む。
「おのれっ!」
「煩いわ。そんなに怒るなら退いて頂戴。船に乗りたいの」
「二の丸様、おやめ下さい。そのようなことをなさってももう……」
割って入ろうとした康政は、ハッとした。気付いたか、と思ったがもう遅い。躊躇無く太刀を振り上げ家康に下ろそうとすれば家臣たちが一気に刀を抜いた。三河武士は忠義者、何代も続いた結束、それは豊臣には得られなかったものだ。半兵衛さま、もしわたしたちが何代か続いた家であったら関ヶ原はなかったでしょうか? 望むべくもないけれど。
「ならぬっ!」
康政が声を張り上げる。目を見開く家康も、走り寄る家臣もゆっくりに見えた。大坂に這ってでも行きたかった。どんな目にあっても。でも連れ戻されそれも叶わぬなら、せめて目の前で死んでやろう。ああ、これで終われる。尼君にだけは、申し訳なく思うけど――
首と背中に強い痛みを感じた。最期に映るのも家康だなんて悔しくて苦しくて涙が出た気がした。