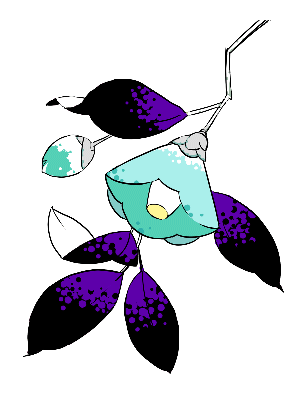
それは時間との勝負だった。あの手この手を使い自分がどの方向へ進んでいるか攪乱するにせよ、男の、しかも忍びの足に敵う道理もない。打開策はただ一つ、いち早く女の一人旅から抜け出すことのみだ。幸いにもかぶき一座と伊勢参りの連れだった一行に混ざり浜松から伊勢へ向かう船に乗ることが出来た為、わたしは今どうにか件の尼君の許へ身を寄せることが出来たのだ。かぶき一座と伊勢参りの組み合わせというと妙なものだが、たとえ用心棒を雇おうと煌びやかな衣裳を運ぶ一座が少人数で移動するよりは、大人数の信心深い一行と行動を共にする方がまだ安全と言うものだ。加えて、皆終着点は一緒でも途中から合流する者も多い、わたしが混ざってもなんの違和感もないのだ。ともあれ、あれこれ悩んだものの結局一番安易な伊勢という行程を選んでしまったが、伊賀を通らずに上方に行く道筋も見えたので良しとせねばなるまい。
「ご機嫌如何にございますか」
障子の開く音がして足を踏み入れた尼君はそう言った。彼女の手には御仏からのおさがりとして饅頭が鎮座している。出入りのある尼寺の住職ともなると”年頃の娘”の存在を隠しきることは難しく、寺の者幾人かには、尼君の遠縁の女が出家を考えて転がり込んできているが出家をやめさせたい尼君が日をかけて説得している、ということにして船も尼君の伝手で用意される手筈になっている。
「尼君」
「さあさあ、よろしければお一つ」
「ありがとう存じます」
この尼君に随分危ない橋を渡らせている負い目が背を丸くさせる。目が合えば彼女が信望する神仏のように笑むばかりでそれが自分を見つけだしてくれた時と重なる。
数日前、伊勢に到着したもののさて次のどう船に乗るか、と迷いながら道々の者らとお休み処に座っていた。そこに現れたのが旧知の尼君だった。彼女はただ伊勢参りの一行を労う為白湯を差し出しに来ただけだったのだが、商人達を見定め何処そこに行くと言いながら欺き、衣裳や小物を金に換えつつ逃避行をしていた身にとっては、これこそが神仏の巡り合わせと言わざるを得なかった。
この尼君、豊臣にゆかりのある女僧なのだが血縁的なものが有るわけではない。ただ、荒廃した伊勢の社の復興の為、豊臣家や朝廷に働きかけついには式年遷宮までやり遂げた女傑だ。元は紀州の奥氏の子女であったというが、にとっては力無くもものの為し方があるのだと教えてくれた人物でもある。
「そのようなお顔をなさいますな。この尼は今生であなたさまに再びお会いできてどれほど嬉しかったか」
「正直……このような巡り合わせがあるなどとは思っておりませんでした。尼君には感謝の一言に尽きます」
「それはきっと御仏か……、太閤殿下のお導きでございましょう」
「此度ばかりはそれを信じております」
それは己が力のみを頼みと豊臣で生きてきた女の言葉とは思えぬものだったに違いない。あの生活の中で自分は確実に何かを削がれている。それでは駄目なのだ。尼君の眸にもそれは映ったに違いない。
「大坂には――」
「え、ああ」
「本当に大坂に行かれるおつもりですか? ――僭越ながら耳にします今の大坂は太閤殿下や石田様がおられた頃とはあまりにも……」
「無論です。この身はもはやなにも持たぬもの。なれどわたくしの生は、亡き竹中半兵衛さまに頂戴したものです。ただ一つ残ったものを師にお返しするはわたくしの勤めと心得ています。たとえそこに何もなくとも」
「さま……」
分かっているのだ。家康の許にいれば静かな一生か女の栄華が待っている。でもそんなものはなから欲しくはない。
「何も仰って下さいますな。亡き者とされ死ぬこともかなわず閉じこめられたあの場所でさえこの心は変わりませんでした。わたくしの生は豊臣の為にこそございます」
「尼は悲しゅうてなりませぬ。これ程のご器量に恵まれておられますのになにゆえ……。なれどもさまがそう望まれますならばこれ以上は申しませぬ。ですがもし、御身お疲れになられましたらまたこの尼をお訪ね下さい」
「……ありがとう存じます」
かくも荒れた世でこんなにも温かい手を差し伸べてくれる人がいることをわたしは知らなかった。僧籍だって禄は要る。だから武器を持ち徒党を組むのだ。ああなんて、この御方は――
伊予の姫巫女は祈祷の為の榊を手に取りながら、ふう、と息を吐いた。江戸を新しい政の地として機能させる為様々なものが築かれていったが、それには魂鎮めは不可欠で彼女は連日の如く駆り出された。それも落ち着きやっと伊予に帰る道すがらのこと、至急だの内府さま直々の頼みだのという早馬が来てあれよあれよと近くの支城に押し込まれてしまった。
「やっとわたしの船の皆さんにもう少しで会えるって時に、はぁ、家康さんの御家中は人使いが荒いですー」
そういえば石田三成を見捨てることが出来ないとあえて西軍に付いた西海の鬼、彼もそれなりの処遇は受けたが四国にいるはずである。久しぶりに憎まれ口の一つもたたいてやろうと思うくらい今の彼女、鶴姫には四国が恋しかった。
「まあいいです。困っている人を助けるのは大切なことですもんね」
さっさと終わらせて帰ればいいのだ。しかし今回の依頼は奇妙なものだった。数日前駿府の城が何者かの襲撃を受けた。その際失せものがでたのでその在処を占って欲しい、というもので、失せものが何かは伏せられた。流石にそんな万能ではないと言ってみたものの、鬼気迫る徳川の重臣の顔に受けざるを得なかったのである。
「何かが分からないんじゃ占いようがないです……。というかてっきり誰に襲撃されたのか占って欲しいって言われると思ってたんですけど、うーん徳川の方の考えることはわかりません」
そうすると控えていた家臣が、徳川内府さまに仇なすといえば一つしかございません、と苦笑混じりに答え、それもそうだと思い直した。天命は徳川の隆盛を示し、豊臣の命数は尽きた。これは何度御神託を得ても変わらなかった。それでも豊臣方はその牙を潜めることはなく、今回もその一つだろう。だが鶴姫は知る。その一つが見過ごせないものになったなら徳川は躊躇なく潰しにくるということを。家康が望まずともそうなる。天がそう示しているのだから。
彼女もあの大戦を経て随分と大人になった。正義や人の心だけではどうにもならないことがある。
「まあとりあえずお聞きしてみます。御家中の方が血相を変えてこられるくらいですからきっと大切なものなのでしょうね」
そうして彼女は二夜に渡って祝詞をあげる羽目になるのだが、依頼の失せものらしきものの神託は下らなかった。ただ西に薄紫の雲が延びているのが視えて源氏物語の終わりようだと感嘆し、それが伊勢の方角であると思い出して、良いものが視れたと妙に納得したのだった。