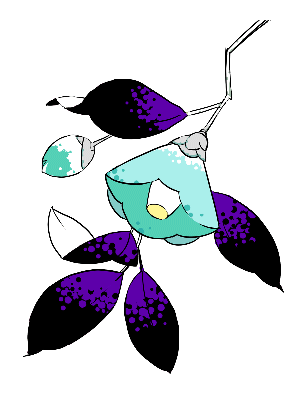
夜の闇を只管に駆ける。駿府の町は城の騒ぎと相まって家々には小さな灯りと大きな通りには煌々と篝火が焚かれ夜目を利かさずとも順調に進んだ。ここを過ぎれば恐らくそれも無くなり後は朝まで身を潜めるしかないが、それもこの馬が何処まで頑張ってくれるかだ。朝になれば城の騒ぎも収まって追手が来るに違いない。否、すでに気付いていると考えるのが妥当だろう。ひょっとしたらもう差し向けられた後かもしれない。となればすぐに街道は閉鎖されてしまう。急いで船を見つけねばならぬだろう。
「頼むわね」
そう言って馬を撫でた。なかなかに毛並みのいい馬だ。そういえば、と独り言ちる。娘と交換したこの小袖は馬臭くないと思った。この馬といい小袖と言い存外大きな馬屋を使ってしまったかもしれない。背に腹は代えられなかったとはいえこれはすぐに足が付くだろう。
「まあそれも織り込み済みだけど」
日が登ったらすぐに古着屋を探さなくては。早く船に乗りたいところだが近くの清水の港は使えないだろうし、その先と言えば浜松、岡崎……いずれも家康の勢力圏が続き、何度も身形を変えて進まねばならぬだろう。数が減ったとはいえ関所を考えればかなりの大回りでも当初の思い付きの通り信濃か甲斐から陸路を行った方が安全かもしれない。そこは家康と相容れぬ武田家の領内であるから。そういえば武田家を纏める真田殿の処遇はいかが相成ったのか。気づけばわたしはあの合戦の後、身近な人以外がどうなったかを知らないでいる。
だが何を考えても状況を打破しなければ先はない。真田殿がどうなったかも大坂に着けば分かることだ。
「所領安堵は考えにくい……か。――どれを選んでも追手は来る。痕跡を分散させて手堅い行程を選ばなければ」
となると陸路はやはり難しいのだ。若い女が一人で険しい道のりを歩むなどただのカモであり追手以前の問題だ。もし甲斐信濃で領主交代が行われていたらなおのこと治安は最悪である。最良は旅の一行に紛れ込むこと、それが自然と出来る道を選ばねばなるまい。
「駿河はだめでも遠州にはいってすぐの港なら伊勢まで……」
真っ当で一番最初浮かぶ道筋だ。それなら連れ合いを亡くした哀れな女のお参りでも罷り通るであろうし、そもそも伊勢ならば秀吉様が橋の造営や途絶えた式年遷宮の復興もした強い縁故がある。自分が足を運んだこともあれば、何よりかの地の復興に尽力したとある寺の尼君とも個人的に親しい。家康の知らない交友関係の一つだ。あの尼君ならば何も言わず匿ってくれるに違いない。
しかし――
「ああ……だめ、その後が」
伊勢の次が問題なのだ。伊勢の次は伊賀、わたしを見張っていたあの服部半蔵の父の出身地であり彼もまた伊賀に強力な縁がある。彼らは忍びだ。わたしの脚よりも遙かに早い。もしかの地の伊賀者が一斉に牙を剥いたらわたしは動けなくなる。
「船は惜しいけど信濃から美濃……」
馬の腹を蹴りながら呟いて、そして溜息が出る。大軍に身を置いて居るときにはついぞ感じなかったこの心細さ、女一人が移動するだけでここまで怯えねばならぬ現実が途方もなく歯がゆい。此処数年軍師としての羽を折られ何も出来ない遼遠の時、それが幾重にも重なる。あそこへ戻る訳にはいかない。太閤や銀の軍師らと共に歩み生き残ったのは自分だけ。せめて太閤最後の血縁の許に馳せ参じることこそが今、生を食んでいる意味なのだ。
「帰る、絶対」
そこにもう友は居なくても。あの絢爛な大坂城に師の残影すら見つけられなくても。
一晩が明けた。幸いにも城内へ放たれた火はすぐに消し止められたが、大坂を攻める為に運び込んでいた兵糧のいくらかは炭と化し、それは出陣の遅れを意味した。なんとも為政者というのは身勝手なもので百姓が汗水垂らして出来上がったものを、という怒りよりも太閤の血縁が延命したのだという現実に焦燥を覚えている。泉下へと消えた友が言うように、やはり我が身は偽善に欺瞞の塊であるのだろう。
気色によく気付く康政などは、なに、休みが出来たと思えばよろしいのです、と言い淡々と事後処理を進め、二、三日中には城の補修と兵糧の手配を付けると宣言した。
皆々よく動いてくれて、ともすれば手も空く。そうなればやはり心は空蝉のように衣だけを残して消えた佳人へと馳せ、また別の苛立ちを呼び起こす。
昨夜大胆にも城で暴れた忍びは予想以上の手練れであったらしく徳川の誇る忍びである服部半蔵でさえ深手を負った。それでも相手にそれ以上の蹂躙を許さなかったのだから褒め称えるに相応しいだろう。その半蔵は未だ目を覚まさず、このまま彼を失ってはと頭を抱えるしかない。
半蔵をそこまで圧倒した慮外者は果たして出陣を遅らせることだけが目的だったのだろうか。のことだ、城内の気配を察し機転だけで逃げ出すことは十分に考えられたが、誰ぞの手を借りての逃亡であったのなら。――が生きていることが漏れていたのなら? がすでに大坂方と通じていたのなら?
「……」
あのように怯えきった顔をして頼りなげにワシを拒みながら内心嘲笑い虎視眈々と機会を窺っていたのなら、いくら彼女でもこれ程癪に障ることはない。もしそうであるならやはりあの男の教え子なのだ。
「竹中……半兵衛……」
名を呟けば一気に瞋恚が燃え滾る。の行動理念は常に彼の役に立つかどうかだった。過激になる太閤や半兵衛の策を女性ながらに制するところがあったにせよ、それもまた豊臣の行く末を案じるが故、半兵衛の評判を気にするが故。彼女自身を思っての行動は今思えば一つとしてなかったかもしれない。
きっと今この時、城から逃げ延びている時でさえ彼女は太閤が築き半兵衛が支えた豊臣を守る、その一心でしか動いてないだろう。改めて思う。は三成と根本は同じだ。その激情が表に出ているかそうでないかの違いなだけで、これと決めた相手に盲信している。
だがよ、おまえは三成を見て分からなかったのか。妄執の先などないのだと。対外的に死したことになっているおまえだ。どうしてもワシを受け入れられないというのであればいっそ別の道を歩んでもよかったではないか。
何故、ワシが大切だと思った人間は揃いも揃ってこうなのだろう。
「失礼申し上げます」
「……は見つかったか?」
「いえ、未だ。何分年若い女人であられる故、近くの町にいらしたような報を得ました時は直ぐにと思うておりましたがなかなかどうして。何度も身形を変え馬を変え……足取りを掴んだと思いましたら、立ち寄る店立ち寄る店でいろんな方角へ去って行かれたり。それでも間違いないと捕まえてみましたら全くの別人。しらみつぶしにあたるとしましても予想以上の数を割かねばなりますまい」
「たかが一日しかも女の身よくも此処まで」
「並の御方ではないと存じ上げておりましたがあのお姿にすっかり騙されておったと痛感しておりまする」
「あれだって偽った訳じゃないさ」
そうだと思いたいのだ。あの男がいない場所でなら彼女は只の手弱女であって欲しいのだ。それが押しつけであろうとも。
「引き続き探してくれ。絶対に傷つけるな」
「はっ! 重々心得ておりまする」
彼らがそう言って去るのはもう何度目のことか。幾度となく彼らの手を借りて、それでも溝は埋まることを知らない。どこかで掠める”もう諦めろ”という理性。それを打破しもっと先へと望む欲。いい加減自分はどちらかの手を取るべきだ。
「いや……」
「は?」
「ワシも行くよ」
「しかし……未だ敵の間者の足取りは掴めておりませぬ。御身の御安泰を考えればどうぞ……」
「……分かった。すまない」
「有り難く……」
顔を伏した家臣は感無量と肩を震わせる。ほら、そうではないか。本当はお行きになりたいでしょうに、という同情と行ってはならぬという建前、ワシがいい顔をするばかりに彼らにもいらぬ心配をかけている。
「ただ、そうだな。一人呼び寄せて欲しい人がいる」
「心得まして」
終わらせるべきなのだ。どちらに転んでも。