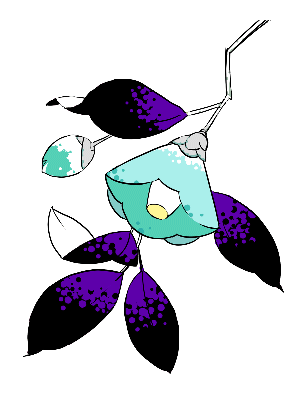
小舟は終着点へとたどり着き、わたしはトン、と舟入りに降り立った。正確な位置は分からないがおそらくここは武家屋敷の建つ三の丸を越えた外堀だろう。すぐそこに大きな門があったが皆動揺して通り抜ける小舟など気にも留めなかった。否、気づいている者も居ただろうがそれどころではなかったのだろう。ザルだ、と思った。皆豊臣方に比べてあまりにもお粗末だった。苦難を乗り越えた家康の旧臣たちならばこのようなことはないであろうが、大大名になってから得た家臣らにはまだその心得が足らないようだ。これが何より今のわたしの助けとなるのだが。
「ありがとう、気にはなるけどわたしではどうしようもなさそう。先を急ぐわ」
そう言い残してわたしは駆ける。
もうすでに夜半だが城の騒ぎは市井にも隠しようがない程のもので町人たちも皆家から出てその様子を覗いていた。何事だ、お殿様はご無事か? 何処が攻めて来たんだ、なら逃げなければ、と口々に言い合い夜とは思えない喧噪ぶりだった。さながらそれは祭りの混雑にも近い。
町人たちが出した灯りを頼りに人の波を掻き分けて馬を探す。獣独特の匂いのする場所はすぐに見つかったが其処は馬借の馬たちで昼間の労働のせいか疲れ切っていた。二、三、路地を進み漸く見つけた馬屋の主人に家康が寄越した小さな茶入を手渡し、足許を見る主人に娘がいることに気付いて着ていた小袖と交換してやって漸く馬を得た。衣服まで換えた自分に馬屋の主人は怪訝そうであった為、ただ一言、主命である、と毅然と言い放って馬の腹を蹴った。風を切り、徐々に喧噪が遠のいて躍動を感じると、この身がやっと家康から離れたのだと実感した。そういえば馬に乗るのは何時振りだろうか。関ヶ原に至るまで内応を促す為彼是と動いたことが思い出されるが、やはり色濃く残るのは敬愛する師と共に馬を駆り幾多の戦場を駆け抜けたことだ。自分が動き回るのは戦となる前、半兵衛と共に地形を見、天候を見、吉凶を見た。自分の意見が採用されなくても、時に厳しい添削が入っても何もかもが輝いた日々。
「……」
もう永遠に帰ってこない旧懐にただ虚しさだけが臓物を抉るようでまた馬の腹を蹴るに至った。
新たな悲鳴を聞きつけて二の丸を出た後、遥か頭上を聞きなれた音がした。
「忠勝!!」
キュイーンという擬音と共に降り立った彼は両脇に半蔵は配下の忍びと家臣を一人抱え不規則に膝を突いた。目を見開いてみれば具足には若干傷がついている。
「大丈夫なのか、忠勝。無理は……」
大事ありません、忠勝の眸はそう語っている。だが両脇に抱えられた忍びらは完全に意識を失っており、敵は認識以上の手練であると思い知らされた。
「まずはこの者らの手当てを。女子衆頼む」
「はいっ」
「忠勝も」
だがやはり彼は拒否し、そんなことより伝えたいことがあるのだと訴えおもむろに掌に乗る手裏剣を見せてきた。小さいが精巧な造りに研がれた手裏剣、その形状には見覚えがあった。
「これは……確か武田の」
何度も刃を交えた勢力、その武具はすでに見慣れたものだ。これだけ派手にやらかすということは軍略的意味合いとは別に宣戦布告でもあるのだろう。
「そうか、真田は……あの男はやはり豊臣に付いたのだな」
「――」
「信尹殿には骨を折らせるだけになってしまったな」
「――」
「忠勝、お前をそれ程手こずらせるということはあの忍びか?」
「――!」
「あの忍びを討つのは至難の業だな。皆の救護と後は追い払うだけでいい。悪いがもうひと働きしてくれるか?」
「……」
だが女子衆に怪我人を渡しながら此方を見る忠勝の眸は厳しく、是としない彼は微動だにしない。
「忠勝?」
「――!!」
忠勝は蜻蛉切を振り切っ先を向けてくる。彼の行動に近侍衆はどよめいたが、尖端がワシではなくその後ろの御殿を指していることに気付きドクリと心臓が鳴った。
様に何かありましたね、仰らないとはなんと水臭い、そう語っている。
ああこの男は――と思わず唇を噛んだ。状況を考えれば彼にはまだ戦闘に立ってもらわなければならないし何より今それを言うのはいけないと理性が押し込めていたのに。だが苦楽を共にした彼にとってはそれこそが侮辱であるのだ。
「おまえは……」
「家康様っ!」
切羽詰まった声音で駆け寄って来たのは康政だった。すぐに膝を突く彼の手や頬に煤が付いている。
「家康様、二の丸様はおられましょうやっ!」
「……」
「やはり……。家康様、水路の舟を任とする者が四半時ほど前に見慣れぬ年若い女子を乗せたと知らせに参りました。その者が申すには女子は自分は新参だと申し心づけにこれを渡してきたと。全く動ぜぬ物言いだったので思わず信じてしまったが冷静に考えればおかしいと某の許へ来た次第にござりまする」
押し黙るワシに康政は手帛紗を広げ、ずいと差し出す。其処に鎮座するのはにと買い求めた異国の装飾品だった。何の汚れ一つついておらずそれが彼女にとって価値のないものだったのだと思い知らされ、気の毒がる康政と近侍の気配に心が痛む。大きく息を吐いて目の前の忠勝と康政をじっと見据えた。
「そうか……」
「家康様……」
「侵入した忍びはどうなっている?」
「まだ城内に居るようです。忠勝殿が此方に下がられる前に半蔵殿が抑えに走られました由」
「半蔵が動けないとは……やはりあの忍びは恐ろしいな」
「誠に」
「忠勝、康政」
「はっ」
「これは私用だ。ごくごく個人的な。他の者に命じたがやはりお前たちに頼みたい。……我儘を、言ってもいいだろうか」
「何なりと!」
「忠勝はわしと一緒に来てくれ。康政はすぐに街道の閉鎖を。半蔵は必ず奴をしのいでくれるはずだから他の者は半蔵の援護を。……頼む」
「御意!!」
「奥の方々は気を強くもってここを守って欲しい。すぐに戻るから」
「心得ましてございます」
「皆頼む」
「はっ!!」
まだ城は落ち着く様相を見せない。だがこの者たちは必ず止めてくれる。そう信じて忠勝の背に足をかけた。