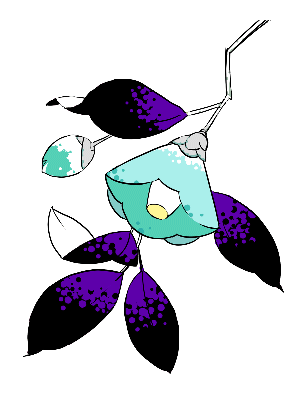
あの忍びの気配も最早遠のいた廊下をひたすらに進んだ。その間も風声鶴唳、鳥の鳴き声にも自身の吐息にさえも怯え、それでも気を奮いようやく奥御殿と外への境である杉戸へと来た。流石にそこにはまばらに人がおり行き来を繰り返している。杉戸にはいつも錠が掛けられておりわたしは近づくことさえ叶わなかったが今は出入りの為か開いたまま。此処を抜ければすぐに水路のはず、それはまるでわたしに放たれた撒き餌のようだと思った。
「一体これは何なのでございますか。攻められているのですかっ」
「そんなっ! 徳川はっ家康様は天下人で御座(おは)しましょう?!」
「ああ、何かが燃える匂いが致しまするっ」
「方々、まずは落ち着かれて!」
慎重に杉戸の辺りを探っていれば、動揺を隠し切れない女たちが口々に不安を吐き忙しなく走る男たちを呼び止めているのが見える。
「兵を向けられたわけではありません。ご覧下さい。城下に火の手はありませぬ」
「さ、左様で、左様にございますね」
「方々におかれては此方に不審な者は来ぬかようお見張りください」
「わ、わかりました」
「まずは薙刀をお手元に」
「はいっ……」
侍女たちは互いを見やって頷くと各々薙刀を取るべく廊下を後にする。去る気配に胸を撫で下ろしながらも、あれでは家康も心許無かろうと思った。これが大坂方であったなら侍女たちは言われずとも薙刀を取り出入口など誰一人通れぬように侍るであろうから。
かつて関東の女は皆勇ましいと聞いていたが今はもう違うようだ。裏を返せばここの女たちは日頃攻められる恐怖とは無縁な幸せな城勤めをしているということだ。
世の流れは確実に徳川に向いている、否応なく思い知らされた気がした。
「……今ね」
だからこそ一刻も早く大阪へ向かわねばならぬと踏み出して杉戸に手をやって抜けた瞬間、
――ドオオオン!
と爆音が響いて御殿どころか城内総てが揺れたように感じた。即座に周囲が阿鼻叫喚になり悲鳴と怒声が入り交じる。わたし自身もまた音には驚いたが、脳裏では冷静に蔵にある火薬か何かに引火したか、天啓だと達観の方が大きかった。
面白いように潜り抜けていく間に、まだ米蔵は無事だった、すぐ護れ、と男たちは慌ただしい。米蔵はこの近くだと思い起こしてピンと背筋を伸ばした。様子を窺っていた方が怪しまれる、そう思ったのだ。
それからは階段を降り手近な草履を拝借して一目散に水路へと足を進め、現れた階段を降りた先にはようやく探し求めたものが鎮座していた。揺蕩う堀の水とこの一艘の小舟がわたしの命運を握っている。すぐ傍の足場で船頭らしき男が櫂を手に忙しく周りを見ていた。
「ああ、此方は無事だったのね。良かったわ」
「へ、あ、はいっ!」
「大丈夫よ。何か来ているようだけど本多様がすぐに動いて下さっているみたいだから。悪いけど家康様の内々の命よ、舟をすぐに出してちょうだい」
「さ、左様で。あの、どちらに? 貴女さまは?」
「変な人、この情勢下何処へ行くなんてわかるでしょう。主命なれば其れ以上言えないわ」
「こ、これは大変失礼を」
「……いえ悪かったわ。顔の知らぬ女に言われれば驚くくらい分かることね。これから何度か世話になると思うわ。よろしくね」
「はっ、ははっ!」
当然のように舟に足をかけると船頭が慌てて手を差し出してくる。気安く礼を言って座りながら、わたしはやや大袈裟に袖の下に手をやった。
「はいこれどうぞ。こちらの流儀がこうかは知らないけどまあ心づけね」
「これはまた」
拝領したのだけど付けないのよね、目立っちゃうの、と言いながら手渡したのは持ちだした装飾品の一つだ。洒落た柄は多分京流れのものだろう。船頭は驚きのまま受け取り口許は緩んでいる。
「……ダメね」
「はぇ?」
「今、外の音聞こえてて? 見慣れぬ顔のわたしが侵入者かもしれないのにホイホイ信じちゃだめよ」
「は、はっはいっ!!」
よくもまあ、と内心ため息が出る。いけしゃあしゃあと嘘が出るもの。撹乱し敵を翻弄するのは軍師としてはお手の物、とはいえ、罪悪を感じるのは何ゆえか。美しい打掛に晒され感性までもが女になってきたというのだろうか。もしそうなら家康は豊臣の軍師の判断力を削ぐことに成功したと言える。
しかしながら目下の男の不信感を減らすことは出来た。水路を越えるまでであればそれで十分、後で矛盾に気づいてもその時わたしはいない。
ゆっくりと進み揺れる小舟、その間にも何処かで悲鳴が聞こえてくる。
「ありゃあ二の丸御門のあたりだ」
「一体何なの」
さも被害者の一人のように言ってのけながら目を顰める。この騒ぎは恐らくあの声の主だろう。やはりあの男はわたしを誰だか知っているのだ。そうして逃がそうとしている。家康と戦うために。
聞いたことのあるような声だったしそうでなかったようでもあるし、否、今はどうでもよい。逃れた先にその答えがあるだろうから。
鎮火と各門の守りの強化及び怪我人の救護などの指示を出した天下人のの足はそのまま奥御殿に向いていた。生きる為逞しさ兼ね備えた下女たちは桶に水を取って走り、対して侍女たちは薙刀を手にする者震える者さまざまだった。家康様家康様と縋る侍女たちの有様にこれは急がねばと内心眉を顰め、まずは付きの女たちを探す。
「誰か! 二の丸殿付きの者は」
しかしながらそう叫ぶと同時に何処からか爆ぜる音が響き女たちの悲鳴にかき消されてしまう。これでは埒があかぬと皆をあしらい近侍と共に聊か強引に進むことにした。平素なら女共にも女共の規律があるのですと止める何某の局も、今ばかりは皆の叱咤に忙しくそれどころではないらしい。杉戸を抜け、徐々に喧噪が小さくなる場所まで進めばそこはの居室だ。
「家康様っ」
「ああ、内府様っ」
薙刀と袴を身に着けた彼女たちは外の者よりは幾らか落ち着いて見えたがそれでも声音は上ずっていた。
「すまない、は?」
「はい、すでにご寝所にお入りあそばしました。先程灯明の油を差しに参りましたが仔猫と戯れておられます」
「ほんに仔猫がお好きでいらっしゃいます。此方は戸が多い為か外の音も小さく、気にも留めておられぬご様子」
「気に留めていない……?」
「如何なさいました?」
「いや、せっかくだ。声だけでも聞いて行こう。まだ寝ていなければいいが」
「心得ました。どうぞこちらへ」
薙刀を持たぬ左手に手燭を置き恭しく先を行く侍女は、足許にお気を付けをと言いながら僅かな芳香を漂わせて進む。の住まう居室から遠いとはいえ、此処は外の喧騒とは違う別世界のように感じられるのは多分身びいきなだけであろう。尤も戸や格子を増やして閉じ込められるにとっては失笑ものだろうが。
「――失礼申し上げます。二の丸様、もうおやすみであらせられますか?」
その声に返答はない。ただ小さく仔猫のものであろう鈴が聞こえるだけだった。
「二の丸様、まだ仔猫と――」
刹那、遠くでドン! という音が響く。侍女がヒ、と息を呑み、近侍が柄に手をやってあたりを見回す気配がする。だが、
――チリン
居室からはその音しかしない。
「――開けてくれ」
「家康様」
「非常の時だ! 開けろ!」
声を荒げてしまったがもう最悪の状況しか浮かんでこなかった。
軍師というのは戦略だけではない。気候を見、まじないを見、あらゆる要素から勝利を導き出す。竹中半兵衛は知略の塊だったが、は戦場に居て鳥の羽ばたきから嵐を、青天の中の雨の匂いも嗅ぎ分けた。女性ゆえかその感性が研ぎ澄まされていたのだ。そのが、こんな大騒ぎに気付かぬものか。ましてワシという存在に怯える日々を過ごす彼女がこの響く音に無関心を通せるはずがないのだ。
「に、二の丸様、失礼申し上げますっ」
侍女が戸を引くと同時に強引に押し入り二つ程乱暴に襖を開ける。主君の無体を咎める余裕は誰にもない。
「っ! 非常の時だ。許してくれ!」
最後の襖をスパン! という擬音と共に開いて声を張り上げる。
だが、其処に広がるのは驚いて部屋の隅に逃げてしまう仔猫の姿ともぬけの殻となった綿の蒲団、そして西陣の几帳をはじめとする調度品が鎮座する美しいだけの居室だった。
「こ、れは……」
「そんな」
「先程までは確かに……っ」
「……っ……」
名を呟けば虚脱と焦燥が一気に爆ぜた。落胆と共に普段動かない顔の筋肉が引きつるのがわかる。きっと今自分は酷い顔をしているだろう。
「……忍びの気配がしない。何をやっていた! なぜここを離れている!」
「も、申し訳ござりませぬっ」
「探せ! ただし傷はつけるな。失敗は許さない!」
「畏まりましたっ」
「はっ」
おそらく初めてワシの勘気というものを見た近侍と侍女はこの世の終わりでも見たかのように蜘蛛の子を散らすように去って行った。彼らの足音が遠のくと、また小さな鈴の音が耳を撫でる。
大声に驚いて几帳の影に隠れた仔猫の眸は愛らしさの塊だった。
「はぁ……」
天を仰ぎ大きく息を吐いて焦燥を霧散させそれに、おいで、と言ってみるも当然寄って来はしない。几帳に近づいて端の飾り結びの施された紐を目の前で揺蕩わせ少し間を置くと警戒していた小さな住人は紐に飛びつく。その際紐の結び目が解けてしまったがどうでも良かった。紐に夢中になる住人をそっと撫でてみると、零れ出た言葉は場違いにも”可愛い”だった。
そしてやはり漏れるのはため息ばかりだ。
こんな愛らしいものを、彼女はあっさりと置いて行った。半兵衛殿の求めたものが我が身の全てであるにとっては執着するべきものではなかったのだろう。
子猫は時折の蒲団へとすり寄り喉を鳴らす。ああもうお前の主人はお前を要らぬというのに。
「ワシと一緒か」
ワシは堪らず仔猫を手に抱いてそう呟いた。