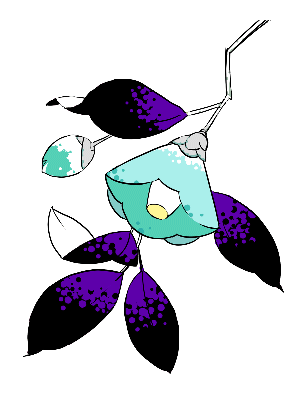
それからしばらく様子を窺っていたが外に出た侍女が戻る気配がなかった。こういう時こそ持ち場を離れるべきではなのだが自分にとっては渡りに船だ。
格子をくぐり襖を抜け、そっと障子を開けると遠くで鐘が鳴っている気がした。広縁の先にはまた格子が巡らされている為それ以上は分からない。しかしながら今は一刻もここを離れることが求められる。わたしは踵を返して水路を目指すことにした。
ナーと仔猫が鳴いた。
「ごめんね」
そう言って撫でて鈴を与えるとすぐに障子を閉めた。チリンチリンと鳴り続ける鈴の音はひた向きで哀れだ。でも早くいかなければ、家康が大坂城を囲む前に。
目指す水路は二の丸御殿のすぐ近く、その水路は清水の港と繋がっている。夜空を見れば雨の気配もない。うまくいけば陸路の半分の日数で大阪に着けるはずだ。
関ヶ原を経て数年、この城に囚われてわたしは初めてこの城を一人で歩く。極力足音を立てず進めるのは大坂で仕込まれた作法の賜物だ。しかしながら長い廊下を進めば存外早く息切れがする。これが年単位で碌に動けなかった証であるのだと思えば腹立たしい。
暫く畳敷きの廊下が続き角を曲がると今まであった灯明の数が減り薄暗くなった。目を凝らして様子を窺い一歩踏み出そうとするが何か嫌な予感がして足が止まる。闇夜が空恐ろしいとは思わない、だがなんと心許無いことか。
「へぇ、良く気付いたね」
「っ!」
突如降りかかる姿なき声に総毛立つ。ばれた! と掛け衿を握り締め上下左右忙しく首を振っても無駄なこと、声の主が何処に居るのか見当もつかない。
「そっちは鴬張りだよ。あっちの右の廊下に行きな」
「誰なの……っ」
嫌な汗が毛穴から滲み出て喉は絞られるようで生きた心地がしない。
「……こりゃ驚いた。まさかあんたとはね。ま、信じて? あんたが生きてるとは驚きだけど逃げてくれればゆくゆくこっちも助かるんだ」
「……」
「右の廊下はそんなに離れてないし今は人もいない。急ぎな」
「……わたしを、知っているの?」
その低音から恐らく男と分かる声の主だが相手はわたしの質問に答える気はないらしく、さてね、と言うと反応がなくなってしまった。そのまま去ったのか息を殺しているのかやはりわたしには定かではないが時が惜しいのも事実だった。
「……信じるわ、どのみち鴬張りを進む勇気はないしここに居たって仕方ないもの。……ありがとう」
返答を待たずに踵を返して道を探れば部屋と部屋の間にも廊下が見える。細心の注意を払い一歩を踏み出せば、怯えながらも心は逸っているのか足はそのままどんどんと進む。最小限の衣擦れの音とともに渡りきり、その先の曲がり角に彼の言う畳の廊下を見つけた時、私は大きく息を吐き次いで生唾を呑みこんだ。まだ油断は出来ない、わたしはまだ廊下を一つ越えたに過ぎないのだから。眼前に広がる長い廊下を私はまた突き進むのだ。
「さすが豊臣の軍師さんだね。まだ折れちゃいないか。頑張りなよ。さて、こっちもそろそろ行くかね」
その後ろで、あの声の主がこう言っていたことも知らずに。
ここ数日、豊臣に攻勢を仕掛けるべく彼是と忙しく動き回り、いよいよ身体にも疲労がたまっていた。普段の何倍にも増えた家臣らの報告の回数と書付の山に今も伸されていたところだ。尤も疲れているのは自分だけではなく、諸大名と交渉したり兵站の差配をする家臣たちも同様だろう。それも多分もうすぐ終わる。
しかし――
「流石に疲れたな」
こんな時いつも通り想を結ぶのは恋うて止まないの顔。今まさに自分が何をしようとしているか彼女の耳に入ればただではすむまい。懸念を決定的なものにし、埋めようのない溝にさらに霧をかけ更にはあの遠き日の存在を消してしまうようなものだ。
だがやらねばならない。でなければ何の為に秀吉公を弑し三成を葬ったのか分からない。そう、そう割り切ったのだ。なのに、三成は諦めたのにを諦めきれないとはなんと俗な男だろうか。
「奮わねば」
今は只、その志を遂げなければ。彼女の心が氷以上に冷え切ってしまっても、永く諸将を説得したようにこの想いで時をかけて。たとえそれが彼女が子の産めない年齢になろうともかまわない。
「……そうなったら康政たちは煩いだろうな」
僅かに笑いが込み上げ、それが虚勢だと思い知る。自分はずっと彼女が欲しい。仮面を張り付けて誤魔化しているにすぎないのだ。
「家康様、御前失礼を。火急にございます」
「ん? どうした?」
随分前に下がるように言った近侍が慌ただしく近寄り切羽詰まった声音でそう告げて来た。
「賊にございます! 三の丸近くの蔵に火が!」
「賊? 火事ではないのか? それで被害は?」
「服部殿が何処かの忍びの姿を確認した由。賊に間違いございませぬ。蔵の被害は三つ程、一つは大豆などを収めたる蔵、あとの二つは具足を収めたるものにございまして今榊原様はじめ皆が火消しに向かっております」
「皆に怪我はないか? 忠勝はどうしている?」
「御蔵番の者らが昏倒させられておりましたがそれ以外は。本多様は服部殿と賊を追われております」
「忠勝が出なければならない程の賊か。厄介だな」
「はっ! 恐れながらこれより某らがご身辺お固め致しまする」
「頼む」
そうして更に焦燥の織り交ぜた促音と喊声に似た声が響き渡る。
「ご注進! ご注進!」
「なんだ」
「一大事にございます! 清水御門に火の手が上がっております! 小火にございますが次は何処にされるかっ」
「なに!」
「忍びか、そのようなものの侵入を許すとは」
「忍びなら撹乱の可能性もあるな。各々落ち着いて持ち場に就くように伝えてくれ」
「はっ!」
どこの手の者か考えるのは止めた。大坂方も、まだ虎視眈々と天下を望む東軍諸将でもあり得た。武具兵糧を焼くだけでも目に見えるだけの効果はある。大坂方を屠り、日ノ本を統一するまでこういうことは続くだろう。
「狙いは兵糧かワシか、いずれにせよ奥の方々に害の無いよう」
「心得て!」
「……」
「家康様?」
”奥御殿”――その単語が脳裏を掠めると冷や水をかけられた心地になる。門や蔵を燃やされたことよりも遥かに焦唇乾舌に値した。
「半蔵は、賊を追っているんだったな?」
「はっ」
「はどうしている……っ」
「に、二の丸様には侍女たちが付いております。先程もそのように報……」
「今一度見てきてくれ」
「御意っ!」
自分でも驚くくらい低い声が響いた。震え上がるように答え足早に去る家臣と近侍が息を呑む音が酷く鮮明に聞こえる。気持ち悪いくらい何かが研ぎ澄まされているようでそれは秀吉公を屠ったあの時に似ていたかもしれない。
障子の先では三河武士たちが鞘をがちゃがちゃと触れ合せながら忙しなく床を蹴り抜けてゆく気配がする。なのに耳に響くのは灯明皿に揺蕩う炎が時折出す小さな音だった。