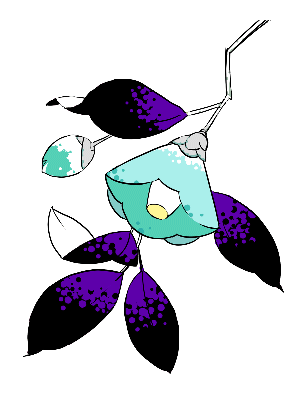
翌朝目を覚ましてみれば部屋の中には細々としたものが増えていた。それは一目瞭然、先日の小さな侵入者の気を引くものであることが分かる。手に取るわたしに侍女たちの満面の笑みが心に刺さって誰にも悟らぬよう息を吐いた。
それから何度か侍女が仔猫を連れて来るから甲斐甲斐しく世話をした。白い客人は厨以外に食べ物と楽しいものがある場所と認識すると気まぐれに顔を出すようになった。お腹がいっぱいになると外へ行こうとする仔猫を追うわたしを格段だれも咎めようとはしない。話を聞いた家康ですら、彼女の好きにさせてあげるといい、と言ったという。とはいえ家康を慮ってか柵や出入り口に近づけば忍びがわざとらしく気配を覗かせ牽制されたが。
それでも”猫好きの二の丸様”の姿を皆が焼き付けるうちに二の丸御殿の近くに厨があることを知った。その先に水路や米蔵がいくつもあることも知った。米蔵には家臣や商人だけでなく近頃は年貢を納める者々が老若男女入れ代わり立ち代わり出入りして、それはあと半月程度で終わることも。そしてそれが終われば皆が戦支度を始めることも。
そろそろ行動を起こさねばならない、その焦りがあった。
ニャーともナーとも聞こえるたどたどしくも愛らしい鳴き声が自分にかまえと抗議を上げる。
「ああ、ごめんね」
いつも通り喉を撫でれば気持ち良さそうな顔を覗かせ小さな手が指に絡みついてきた。なんて罪のない可愛い仕草なんだろう。人並みに嫁ぎ母となったならこのように頬を緩ませながら赤子を抱いていたのかもしれない。
「あら、あなた首が苦しいの? 大人しくして、取ってあげる」
ほのかに湧いた感情に内心首を振り仔猫の首に巻かれた紐に手を伸ばす。この子は別に苦しくもしてないのだけれどわたしにはこのチリンと鳴る鈴が邪魔だった。緩く結ばれた紐は簡単に解け、仔猫に見えるように振ってやった。
「ふふ、首に着けるよりこうやって遊んだ方が楽しいものね?」
無邪気に飛びつく仔猫に小さな罪悪感が募る一方、良くも悪くもこの鈴が鳴れば二の丸様が一緒だと思われているから、わたしとしてはこの子が鈴に興味を持つように少し手を加えておきたかった。
「上手ね、そう、上手」
上げ下げされる紐と鈴に思惑通り仔猫は釘付けだ。つい先程まで自分の首についていたというのに新しい玩具を得たように飛び跳ねて、突いて、食んでみて、と兎角目を楽しませる。愛らしさからなのかそれとも罪悪感なのからか要領を得ないがわたしは仔猫を膝に抱いて相手をした。
「……この色も素敵だけど新しい飾りがあった方が良いかしら。あなたは真白だからきっと菫や藤紫が映え……」
ふわふわの毛並みはそれだけで険をとるのか、誘われるようにそんな言葉が吐いて出て、その後追いかけて来た感情が喉を詰まらせる。俄かに瞼の裏に映る姿は郷愁と侘しさを伴い、次いで滂沱を呼び起こした。
わたしの師は、友は、自分のことなど気にも留めず只理想に邁進する真白で紫色の似合う人たちだった。、と名を呼び陣立の出来を褒めた佳人、その陣立を見て、貴様にすべて任せているとぶっきら棒だが信頼を置いてくれた僚友、何故二人は消えてしまったのか。二人だけではない。秀吉様も刑部も、明るくていつも皆の心を和らげていた左近も。消えるなんて思ってもみなかったのに。
なんと気弱になったものか、たかが仔猫の毛色と首を飾る紐ぐらいで思い出し肩を震わせて枯れたはずの涙を引きずり出すなど。
「二の丸様……」
「……彼方へ、行っていて」
「心得ました」
侍女たちが去る音も、彼女たちが家康に報告するであろうこともどうでも良かった。
なんと嘆かわしい、半兵衛さまのお傍で才を揮い三成や刑部、左近や家康と対等に渡り合い戦場に参陣し幸せを謳歌したあの日々はもう戻ってこない。あの日々がずっと続くと思っていた。居心地が良すぎて軍師である自分しか想像が付かなかった。いっそ、関ヶ原に至る前に諸将の誰かの妻になっていれば城が攻められた折に自害も出来たろうし家康もこのような所業に至らなかったかもしれない。今更後の祭り、常々思い知らされるのは我が身の力無さと虚しさだけだ。
膝の上の仔猫が動かなくなった鈴にそっと触れては手をひっこめる。やがて安全だと分かるとまた噛みつきじゃれるのだが、その真白が薄っすらと掛かる秋の虹さえも溶かしていくようでまた涙が止まらなくなるのだ。
その日の夜のことだった。既に白小袖を纏い床に着くばかりだったのだが、遠くで何か物音がした気がして格子の先をぼんやりと眺めていた。闇夜のはずが外は俄かに明るく、そしてなにかざわついていた。陣ぶれでもないのにいつも以上に篝火が焚かれ時折外では、「二の丸様は?」「お変わりなくお過ごしです」との問答も聞こえる。
そのうち天井裏の忍びが戻っては何処かに飛び立つ気配がする。何時家康が来るかという恐怖からいつも耳を澄まし、塵を舞わす微かな空気の流れにも息を潜めて過ごしているうちに、木の軋む小さな音もわずかな衣擦れもいつの頃か分かるようになった。それは素人に少し毛の生えた程度の武しか持ち合わせなかった私がこの軟禁生活で得た数少ないものだ。
自分から離れるこのとなかった忍びがその職務を粗雑にせねばならぬ程の事態、余程まずいことが起こったのだと容易に想像が付く。
――今しかない。
そう思えたのだ。
仔猫の首にかかる紐を外しちらつかせて見せれば小さな住人は転がる鈴に釘づけだ。すると見計らったように外から声がかかる。
「二の丸様」
「何か?」
「深更とまではいきませぬが遅くなってまいりました。猫をこちらでお預かり致したほうがよいかと思い……」
「……この子と居たいの。もう少ししたら休むし貴女たちを呼び出したりしないから今日はもう下がっていて」
「心得ました。では油の量だけ確かめさせて下さいまし」
「どうぞ」
そう答えるとすぐさま開く襖の音は酷く性急に感じた。一件恭しく頭を下げ灯明皿に寄る侍女だが彼女の目は異変がないか注意深く動いている。格段口をきく間柄でもないし、小さな機微に気付いたと思われては警戒される。わたしは猫とただ戯れてやり過ごすことにした。やがて油を足して去る彼女の背からは露骨にホッとする気配がして、いよいよ今であると腹に力が入る。
間違いない、かつてない混乱がこの城を襲っている。
「仔猫ちゃん、お願いね」
のどを撫でてやれば満足そうな鳴き声がして、ふと笑いが漏れた。此処まで一緒に居たのだから名前の一つも付けてやればいいものを。侍女にも言われたのだ、何故名を付けないのかと。愛着がわいて失うのが怖いのだとわたしは答えた。そんなものは嘘。こんなあどけないものまで利用して逃げ出そうとする自分の浅ましさに目を覆いたいだけだ。
考えても止めどないこと、そう思ってわたしは奮い立つ。打掛は衣桁に掛け、代わりに今日着ていた小袖と手近な乱れ箱の中の小袖を着こんだ。袖の下には同じく乱れ箱にあった細帯と、飾り棚にあった小さな調度品を入れた。家康や商人らが持って来た櫛やら何やら、だ。艶やかすぎる打掛は目立ち足が付く。小袖ならば身軽に動け売る時は脱げばいい。夜が明けて道々の小間物屋と古着屋に売り、馬を得ればなんとでもなる。駿河を抜け信濃に入れば徳川の影響力も弱まる。それでも関所が難しいなら船に乗る算段を付け幾らか握らせればいい。
しかし心許無い。この場には匕首一つない。あれだけ自害を繰り返せば取り上げられて当然ではあるが。
それも城を出てから得ればいいだけのこと。わたしにとってここが正念場なのだ。
「さあ寝ましょう、これで遊ぶのはもう少しだけよ?」
そう言った声はわざとらしく聞こえただろうか?