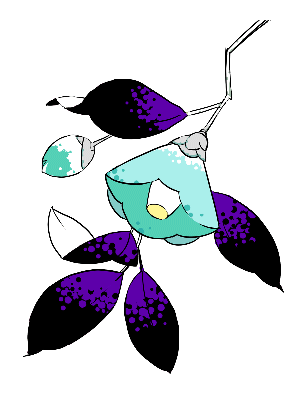
櫓から戻れば外側に格子が巡るには似つかわしくない華美な部屋がそこに在る。居室である一の間の先は襖で仕切られた二の間、三の間、障子と続き、廊下があるがその先は先述の格子が覆い、私に不審な動きがあればさらに舞良戸を巡らされ外が見えなくなる。侍女がたまに開けてくれなければわたしは小さな窓から外を見る事しか出来ない。部屋は美しい、だがここは座敷牢といっても差し支えないだろう。
死したはずの西軍の軍師であるのだから仕方がないと言えばそうだ。現にわたしは今逃げ出そうと心に決めたのだから家康の判断は正しかったと言える。
「二の丸様……」
ただ立ち尽くすわたしに恐れと戸惑いを織り込んだような侍女たちの声が耳を撫でる。彼女たちからすれば善意なのだろうがわたしには大きな悪意に他ならない。
「……貴女たち、家康があそこに来ることを知っていたのね」
「いえ、そのような……」
「わたしは色んな駆け引きを見て来たわ。あれが偶然と思えるほど児戯をしてきたではないの。余計な気を回されてもわたしは応えられないから、もう、止めて頂戴」
「……」
「哀れになるのは貴女たちの家康よ」
「二の丸様の御目には家康様が映らないのですか……」
「映してはならないのよ。分かって」
侍女はそれ以上何も言わなかった。それ以上無理強いすればわたしがまた自害を試みようとすると懸念がよぎったのかもしれない。
「外が見たいわ。今日くらいいいでしょう?」
誰とも目を合わすことなく畳みかけるようにそう言った。わざわざ見なくてもどこぞにくノ一や忍びが潜んでいる。ピンと空気が張った気がしたが無言のまま舞良戸は開かれて格子をくぐることなく外を見た。相変わらず眩しい光を放つ庭、只々落胆が襲い来る。庭には塀の手前に柵が為されるばかりでその景観は平穏とは程遠い。
「せっかくの庭が台無しね」
そう呟けばいちいち侍女たちが揺れ動く。彼女たちから見れば今日のわたしは何時になく攻撃的に映るのだろう。わたしは注意深く、けれど誰にも気取られないよう事も無げを装って庭を見回した。目につくのは柵と季節の花々ばかりでよく手入れがされている。当然のように出入り口などなく、暫く眺めたがそれらしいものはやはり見当たらなかった。
「また、庭を見せて頂戴。……流石にどうにかなりそうよ」
焦ってはならない、もっと回数を重ねて探すのだ。思慮を巡らせながら衿先を引いて身を翻せばやはり侍女たちの息が漏れ出でる。このままわたしが我を忘れて暴れるのかとでも思ったのか。考えれば彼女たちも災難なことだ。ただの女主人に仕えるだけであれば彼是と気を回さずに済んだはずだ。
まだこの身を吹き抜ける風に冷たさはない。だが脳は逃げると決めた時から真冬の白雪の中に居るようにキンと冷えたままだ。眸に半兵衛さまの許で采配を振るったあの頃の光が宿るのを感じながら家康の作った牢へと戻る。籠の中の鳥に甘んじてなるものか。今この時からわたしの逃走劇は始まるのだ。
それから十日ばかり時を経た。
相変わらず格子や庭先の柵を取り払われることはなかったが、外を見たいと言えば最初は警戒していた侍女たちも徐々に率先して誘導してくるようになった。今日は何処其処へ行かれますか? と聞かれたが、侍女たちの気持ちが緩もうと天井裏や軒下で息を殺す忍びらは油断などせぬだろうし、どこへ足を運んだかであらゆる手を打って来る。そして総て家康へと報告するだろうから。
「二の丸様はお花がお好きなのですか?」
「え?」
「家康様がお持ちになった書冊には目を御向けになりませんでしたのにお庭の花々は何度も見返しておられまする故」
「家康が持って来るのは兵法書よ。そんなもの読んで何の役に立つの? 時間があれば読んでいたのは昔。あくまで行軍の采配の為」
「あ、あの」
「花はいいわ。罪がないもの。何も持たないわたしには花を眺めるだけで十分だわ」
「二の丸様……」
「何もお持ちにならないのなら、新しく何かお持ちください。どうか」
侍女もそして侍女と同じように小袖を着て控えるくノ一も総じて悲壮な顔をする。本当に悲しいのはわたしだ。そんな目を向けるなら逃すか家康から遠ざけてくれればいいものを。
「貴方たちは本当に家康が好きなのね」
「家康様はお優しく比類なきご主君にあらせられます。二の丸様、ほんの少しでいいのです。家康様のお目を見て差し上げて下さい」
「もし、その家康が誰ぞに攻められて倒れたら貴方たちはすぐに仰ぐ旗を変える?」
「……」
「そういうことよ」
この悪意無き善意が絶えずわたしを追い詰める。どれ程心の奥底でもがいても誰もそれに気づきはしないのだ。
「格子の先の……あの薄紫の花は綺麗ね」
「あ、はい。あれは枸杞(クコ)にござりまする。実がなれば其れをお薬にしたり麦飯に混ぜ込んだり致しまする」
こうやって彼女たちの懇願をやり過ごすのも何時ものこと。打っても響かないわたしに彼女たちも少なからず遣る方無い想いを抱いているはずだ。もし家康が踏み込んで来たら彼女たちは止めもしないだろう。無論一番は一刻も早く大坂に参陣することだが彼女たちが暴走する前に此処を去らねばならない。
せめてこの枸杞の隙間の先にあるのが壁ではなく抜け穴であるのならほんの少しでも心の平安を得ることが出来たことだろう。だが現実は頑丈な塀が広がるのみ、この塀も格子も限りがあって出入り口があるはずなのだがわたしには限りなく遠く思え、我知らず深いため息が出る。
「何もないところへ行きたいわ……」
「……」
嗚呼、そう言うとこの人たちは何故殊更傷ついた顔をするのだろう。傷ついて、打ちのめされているのはわたしだというのに。分かっているのだ。このままではわたしが此処から出れるのは死んだ時くらいだと。そしてその死すら選べぬのに。だからそんな顔を向けるのは止めて欲しい。それもまたわたしには辛いのだ。
寂寥に包まれるまま身を晒していればチリンと鈴の音がする。なんだろうかと視線をやる前にすぐそばの侍女が、ああこれっ、と声を上げた。微かにしか聞こえない物音は人のものではなくもっと小さなものだ。
「……猫?」
「申し訳ございません。先日城の近くで拾われたのですが迷い込んでしまったようです。普段は此方に上がらぬようしておるのですが」
「仕方がないわ。人間の都合なんてこの子には分からないもの」
侵入者は殊の外小ぶりで白く丸い。か細い鳴き声が生まれてから年を越していないことが窺え、その幼さ故に警戒心などまるでなく手を差し伸べれば簡単に寄って来る。無垢という言葉がぴったりだと思った。
「可愛い」
喉元を撫でれば気持ち良さそうにゴロゴロと鳴る。大坂の城にも可愛らしい猫は何匹もいた。だが半兵衛さまが胸の病を患われると城の端の櫓に追いやられてしまったのを思い出す。
「城の近くで拾われたと言ったけど母猫はいなかったの?」
「聞いたところによりますと母猫も兄弟も野犬に……。怪我をしておりましたがこの子だけが生きておったそうです」
「そう、あなた一人なのね」
応えるように聞こえる鳴き声がいじらしい。しばらく撫でていたがそれに飽きたのか仔猫は柵をくぐって行ってしまった。猫というのは羨ましい。自身の頭ほどの大きさがあればどこでも通り抜けていける。自分もそう掻い潜っていけたなら――そこではっとした。
「――あの子、だれかの飼い猫と決まっていて?」
「いいえ、下女や侍女たちが世話を焼いているだけにございます」
「ならあの子が此処に来るの止めなくていいわ。わたしもたまに撫でてみたいの」
「まあ、ええっ是非に」
誰のものでもなく城で飼っているだけなら縦横無尽に歩き回る仔猫を追うと称して制約はあるにせよ警戒されず城内を探ることが出来るはずだ。抜け道でなくてもいい、何か隙を見つけることは出来ないだろうか。そうすれば、きっと。
侍女たちは二の丸様がようやく明るくなられたと頬を緩めるばかりで女主人が何を考えているか察することなく頷き合っている。罪悪感がない訳ではないがこれがただ一筋の光明だった。