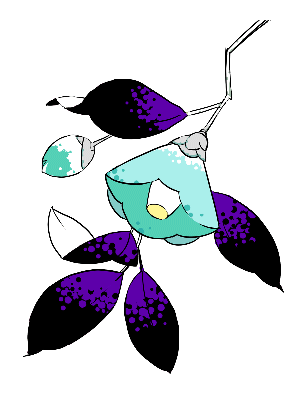
「相も変わらず頑なであられる」
そう声を掛けてきたのは側近中の側近榊原康政だった。鴨頭草(つきくさ)の軍師殿と呼ばれた頃のとも顔を合わせたこともあるからかあまり批判をしない男であったが二年という歳月は彼にも心境の変化を齎したようである。
「家康様の仰る通り、女だてらにあそこまでの忠義なかなか出来るものではないとは思いますが」
「ああ」
「しかしながら某にはそれが哀れでなりません」
「哀れ? おまえは呆れでもしているのかと思っていたが」
「まさか! 某が申したいのは望んでも手に入れる事の出来ぬものを昏い水底で探し続ける二の丸様のなさりようでございます。竹中半兵衛殿はなんとむごいことを教え込んだものです」
「むごい、か」
「御意。恩と忠義の妄執にござる。度が過ぎれば誰も幸せになり申さぬ」
「康政、それは勝者だから言える意見だ」
「左様にございましょうな。しかしながら勝者であるからこそ矯めることもまた責務かと」
「……」
「家康様……」
康政の言葉に押し黙っていると不安気な女たちの声が耳を撫でる。先の夜訪れた苦しい想いを抱いた娘とは違う上等な小袖が眩しく、そしてそれは事の為し方を覚えた彼女たちの特権に思えた。
「ああ、真面に顔を見たのは本当に久々だ。気を回してくれたんだろう?」
「誠に申し訳なきことを致しました。けれどどちら様のお苦しみも早う明けて欲しいとただその一念……」
「分かっているよ」
「しかしながらなんとも……。狂い、いたずらに大乱を起こした凶王とは違います。常に戦を止めようとなさった二の丸様には西軍の将ではなく女子としての人生がおありになるはず。今孔明様の御師事を得た二の丸様ならそれがお分かりにならぬはずはありますまいに」
「……三成を狂わせたのはワシだよ。をただの女子として生かそうとしているのもワシの勝手なんだ」
「そのような、家康様は太平を望まれ、想い人を御救いしようとなさっただけにござりますれば」
「何かを変えようとすれば何かを失う、そういうことだろうな……」
の献身を哀れと言う者もいれば愚かと言う者もいる。それは自分の蜂起を天下の為と言う者と裏切者と言う者がいるのと同じだ。なれば後者の目には彼女をひたすら待つ自分はさぞ滑稽に映っていることだろう。
自らを戒飭するように言いながら櫓の外に広がる駿府の美しい景色を見る。長い人質時代を過ごしたこの地に城を建てたことを家臣たちはとても訝しんだ。三河の家臣らの当時の処遇を聞けばとても心が痛むが、自分自身は厚遇され駿府での人質時代はそれ程辛いものではなかった。勿論不和がなかった訳ではないが、良い思い出が多かったのだ。加えて東と西双方に睨みを利かすことのできる場所となればそれに何の躊躇もない。このことをワシは生涯口にすることはないだろう。ただ軋轢を生む行為でしかないと知っているから。
「家康様」
「うん?」
「飛ばしておりました草が戻ってまいりました」
「そうか」
耳傍を風が掠めたと感じると、重臣たちの後ろに伊賀者の頭領が畏まっていた。その容姿を包み隠さず見せる真田と上杉の忍びとは違い、彼服部半蔵は頭巾で顔を覆い隠しその様は誰よりも忍びたらんとしているように見えてワシにはそれに確かな信頼を感じている。
側近の一人が侍女らに去るようパチリとかわほりを鳴らせば彼女たちは一礼して手際良く下がっていく。豊臣程華美ではないがやはり彼女たちは美しかった。
「大坂方の様子はどうだった?」
「畏れながら不穏の兆し有り」
「……」
「関ヶ原以降減封改易となりました諸将に檄文を飛ばしておるようにございます」
「やはりそうなるか」
「ことに真田幸村率いる武田軍などはそちらに流れる危険性が」
「真田はそうだろうな……。信玄公の志を継ぐ者、共に先に行ければと思ったが関ヶ原の折と変わらなかったか。いや、それもあの男の信念か」
「いずれにせよ厄介な勢力となることは間違いないかと。今一度調略致しますか?」
「無駄だろうが、諦めたくはない。彼の叔父に説得を頼んでくれ」
「心得ました」
すでに日ノ本の形勢は決まっている。伊達や前田などの有力諸将は総じて徳川に付いた。太閤亡き豊臣に付くのは恩顧の者らか、改易などによって行き場を失った牢人たちくらいだろう。たが真田は違った。かの家は豊臣にそれ程縁故があった訳ではない。が、一度として徳川に靡く素振りを見せなかった。要は自身と幸村は相容れないのだ。
「独眼竜が認める程の男、惜しゅうございますな」
「考えればあの二人が足並みを揃えるのもおかしな話かもしれないな。このワシもか」
「家康様」
「……早速に真田信尹殿に使いを送ります」
「頼むよ。半蔵は引き続き各大名の動向を調べてくれ」
「御意」
「いよいよ、大詰めでございますな」
「ああ」
そう相槌を打てば、ふうと息が漏れ出ですぐに、いけない、と思ったときには康政の顔が酷く心配気に顰められていた。
「やはりご心労多くあらせられますな。暫しおやすみになられた方が」
「いや、大丈夫」
「しかし……」
「何かをしていた方が楽なんだ。駆け引きも正直好きではないが嫌なことは早く済ませた方がいいだろう?」
「……家康様、どのような想いで反旗を翻されたか我らはようわかっております。石田殿のこと二の丸様のこと……故に思うのです。やはり貴方さまには支えが要りまする」
「ワシにはお前たちがいるよ」
「そうお気持ちを誤魔化してばかりでは本当に参ってしまいます。せめて我らに出来ることを仰って下さい。ただ一つの我儘なれば皆が許しましょう程に」
「……康政、それ以上は言わないでくれ」
「は……」
そう言って引き下がった康政は多分苦虫を噛み潰したような顔をしているだろう。どれだけ彼や忠勝がワシを心配してくれているかは痛いほど分かっている。それが得難い忠勤であることも。
ワシはこの上なく疲れている。この心を包んでくれる何かが欲しいと求めている。
だから康政や皆の言葉は堪えがたい甘い誘惑だった。やめてくれ、今のワシは求めれば手に入れることが出来てしまうのだ。だがそれは彼女の心を殺すことを意味する。
「まだだ、まだワシは待てる……」
そう、まだ時はあるのだ。急いで手に入れて壊すことはない。だがもし、すでにが誰かの手の中に在ったなら。それ故の頑なさであったなら。
「康政、戻ろう。今日の政務をさっさと片付けてしまおう」
「はっ……」
振り返ったワシは上手く笑えていただろうか。