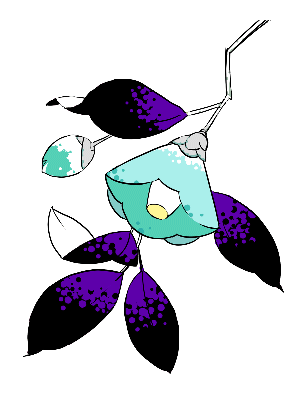
雨の季節が過ぎ、夏ももう終わろうとしている。夜は冷えることから侍女たちは早めの衣替えとばかりし少しずつ冬の衣裳の用意をし始め、二の丸にも俄かにその喧騒が聞こえていた。格子が張り巡らされているものの、最近自害に及ぶことのなくなったわたしへの警戒が緩んでいるのか、近くの櫓に上ることも出来るようになった。そうすることでわたしの気を高揚させようとする狙いであるらしい。尤もその櫓も逃げおおせることの出来ないような堅固な造りになっているのだが。
「綺麗な眺めね」
「はい、徳川の威信をかけた城と城下でありますれば」
侍女らは笑んだがわたしは別のことを考えていた。この城は攻めにくい、逃げ出すには隙が無い、と。此処へ立ち入ることに半蔵らが何も言わないのは余程の自信の表れだ。
二の丸の櫓からは三の丸の様子もよく見えた。其処でわたしは違和感に気付く。
なぜこの時期に米の移動をしているのだろう?
災害が起こった訳でもない、稲刈りにはまだ遠いこの季節に大量の兵糧を忙しく運搬する、とくれば簡単なこと。戦の為だ。関ヶ原よりもう二年も経つ。西軍諸将の接収がうまくいかない訳でもあるまい。もしや東軍に離反が出たか、所詮は利害関係で組した者たち。天下を掴む者が近くに現れたら掠め取ろうとするのが道理なのかもしれない。
わたしはすぐに視線を外した。
「駿府はいい場所ね。海のものも山のものも不自由しないわ」
「はい、駿府の初春は鯛が美味しゅうございまして興津鯛というものがございます。残念ながら今はその季節ではございませぬが、……そうそう年中通しては安倍川の金な粉餅というのが美味しゅうございます」
「そう」
「家康様もお好きなんですよ。明日のお八つにお持ち致しますね」
恐らくその餅の由来にもなった安倍川河口は無防備そうに見えて遠浅の海岸が広がっている。船で攻めるには接岸できる岸壁に止める必要があるが、遠浅の海岸は其れを拒む。接近すれば座礁するのだ。船を止めることが叶わなければ兵は飛び降りるしかない。温厚そうに見えてえげつないことをする、家康そのものだと思った。
「言い得て妙ね」
「はい?」
「なんでもないわ。多めに頼んでおいて、貴方たちの分も」
「まあ、まあ……二の丸様」
そう言って、どうにかして家康の話題を出したり引き合わそうとする侍女たちをかわして打掛を翻す。これ以上家康のことを思い出すのが嫌だったのだ。これから豊臣の思い出は増えない。生きれば生きるほど家康だけが蓄積されていくのが分かるから必要以上に増やしたくはない。いつか、この身が家康とこの城しか思い出せなくなるのがたまらなく怖いのだ。
「あっ」
「――ッ!」
踵を返した先で足音と侍女の驚いた声が聞こえ、反射的にそちらを見た時わたしは息を呑み咄嗟に動けなかった。其処には会えば最も心苦しくなり一番遭遇したくない人間が近侍を伴い足を踏み入れる姿があった。
「ああ、女子衆で息抜きかい? 悪いことをしたね。……ァ、――っ……!」
「……ぃ、っ」
「に、二の丸様、ご着座申し上げて……」
彼、家康は相変わらず人好きのする笑顔を侍女らに振り撒く。こうやって人の心を掴んでいくのだと歯がゆくなるも彼がわたしの姿を見止めて近づくに、此方は後ずさりして逃げるしかない。戦場で敵と対峙しても怯まぬわたしが家康一人に胸においた掌を握り締めて、ただの乙女のように何も出来なくなるのだから刑部あたりがみたら嘲笑するというものだ。
「、怯えないで」
「来ないでっ」
「二の丸様どうか」
喜びと戸惑いを持って近づいてくる家康と眉を下げて妥協を促す侍女の眸がわたしを一方的な悪者に仕立て上げるようで甚い。受け入れて欲しい、此処まで愛されているのだからその手を取ればいいのに、と臭う態度に追い詰められてゆく。
「近寄らないで」
「待ってくれっ」
「放してっ」
逃げる場所は家康の後ろにしかなく通り抜けようとすれば難なく腕を掴まれてしまう。触れる手は大きくて温かく元来彼の持つ陽だまりのようなあの佇まいを思い起こさせるに十分だった。
「お願いよ家康、……放し、て」
「……すまない」
家康は苦しそうにわたしを解放し離れた。振り向かず逃げるわたしに、侍女らが忙しく二の丸様お待ちください、と追い縋るがどうにも振り返る気にはなれなかった。死ぬことを許さぬなら、これ以上わたしを翻弄しないで欲しい。なんの栄光もなくても構わない。ただ豊臣に殉じさせて。それだけなのだ。
なのに――
「二の丸様っ」
「いいっ」
「家康様、しかし」
「いいんだ。ワシは彼女から総てを奪った。そうされても仕方ないんだ。皆気長に待ってくれ。靡かない彼女だからこそワシは……」
耳を突くその聲が痛い。とても小さな声だけど聞こえてる。いつからか家康の声だけが凄く聞こえるようになった。ああそれってもう私は取り返しのつかないくらい家康に浸食されてるってこのことなんじゃないの? いやよ、駄目よ、そんなの絶対。
長局の横の廊下を行けば女たちの声が耳を突く。ここは侍女たちの私室に割り当てられている。尤も数人で就寝と身を整えるだけの狭いものだが。止めどない話は上役の侍女に対する文句であったり、城下へ降りた時の話であったり、家中の誰が素敵であったり、大坂城もこのようであったと思えば瞼が忙しく涙を誘う。
でもそれもすぐに終わりを告げた。角を過ぎて三つめの部屋を通り過ぎる時に聞こえた話が脳を大きく揺さぶったのだ。
「まあ、とうとう?」
「ええ、表でそう言ってたわ。家康様はとうとう大坂城をお攻めになるのですって」
「これで名実ともに徳川の天下ね」
「――っ!」
そんな、と脳が悲鳴を上げたが、ほんの少しだけ冷静に考えれば稚児でも分かることだった。未だ燻る前政権など一利もなく滅ぼしてしかるべき、ただその時が来ただけに過ぎない。だけどあの城に残った豊臣最後の血縁は小さな童のはずだ。そして城内に実戦経験のある者はいるのだろうか。殆どが関ヶ原を機に去り、今ではろくな戦歴のない者らが実権を握っている。日ノ本の歴戦の諸将の殆どを敵にして無事に生き残れるはずもない。
ああ家康、やはり貴方は一途で人の良さそうな顔をして甘い文言を並べておいて裏では冷酷に事を進めていくのね。それならいっそ塵芥のように見向きもしないでくれればいいのに。
家康に対する絶望と豊臣の衰退に喉元が締められるようで苦しい。
無常だ。かつて強さと栄華を誇った豊臣が赤子の手をひねる様に伸されようとしている。半兵衛さまが生きていれば、秀吉さまがお倒れにならなければ、三成や左近がいれば、刑部のように鬼謀を巡らせることが出来るものがいれば……!
――いるではないか。
今此処に、生きて、知略を使える人間がいるではないか。この身は、この脳はその時の為にあるのではなかったか。
今わたしは自害を止めて久しく皆の目が緩んでいる。あの堅固な構えや選り抜きの忍びもおれども所詮は人。何かの隙を突くことは出来ぬだろうか。空虚な生を送れと強いられ半ば諦めていたが、今こそが命の使いどころなのだ。
脳がすっと冴えていくのを感じながら、わたしは歩調も態度も変えず廊下を行く。なんとか欺いて大坂城へ行かねば。この命の最後の踏ん張りどころなのだから。