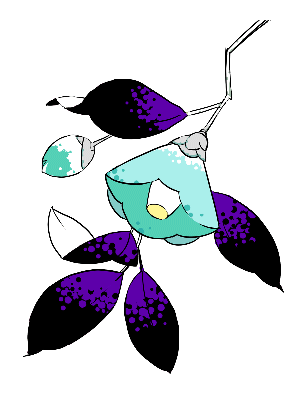
わたしの人生の始まりは何時であったろうか。母の胎内から生まれ出でた時ではない。生きていると、体中で感じる事の出来た日のことだ。
脳裏を染めるのは美しい銀の髪と柔らかな微笑み。差し出された手を取って握り返された時、わたしの産声が上がったのだと思う。
駿府の城の一角で春を二回ほど見送ったある時、それまで江戸への行き来から城を空けることの多かった家康が正式に駿府城に居を移した。わたしにとっては戸惑いと憂鬱極まりないことだけど城内は活気立っているようだ。
家康は毎日のように此処二の丸に足を運ぶ。花を一輪手にしていることもあれば、わたしの興味を引きそうな書冊を持っていることもある。一度障子越しに覗き見てみれば真摯で切なそうな視線がわたしを見ていた。やはりだめだと思った。二、三言葉を交わしてその眸に捉えられたらわたしの根幹が砂のように消えてしまう。
家康を拒絶し彼の背中が遠のく度に侍女やくの一たちの視線が痛い。家康への強い同情と頑ななわたしへの非難が込められている。一度、天下人に此処まで愛されて何が不満なのですか、と問われ、豊臣の女に徳川の子を孕めとは笑止と首を振ったが、乱世なれば普通のこと、すでに様は東軍所属のとある大名の娘との肩書きがございますので問題ございません、と返されてしまった。外堀を埋める家康らしいやり方で、何事も順調に運ぶ方法だと思う。
だけど家康、違うのよ。わたしは揺らいではいけないの。
今日も家康の背を見送った。山吹色の衣裳はわたしには眩しくて輝かしい道を行く彼との隔たりを感じる。すでに陰の道しか残されぬ自身が惨めでありもうそれでもいいと思えたり。いずれにせよ家康と自分が同じ未来を進むなどあり得ない。
死ぬことが許されぬのなら、ただ瞼に映る激しくも美しい日々と懐かしい佳人との思い出だけを思い描いて生きて行こうと決めている。最早それだけがわたしの矜持だった。
「半兵衛さま……」
わたしを救い上げて下さったあの御方が見たらなんと仰るだろうか。何をしているのだと、やはり女子の枠を超えられなかったかと呆れられるだろうか。何一つ果たせぬのなら、敬愛する恩師に殉じてしまえば良かったのだ。
実際、半兵衛さまが死の床に付かれた時はそうするつもりだった。しかし今際の際、皆に先に逝くことを詫び一人一人に訓戒を残し、最後にわたしの手を取って仰ったのだ。すまなかったと。
『こんなに気立てよく育ったのに、どこぞに嫁がせてあげればよかったんだけど、土が水を吸うように覚えていく君に教えるのが楽しくて永く手許においてしまった。戦場にも出して見たくないものを沢山見せてしまった』
賢人がそんな後悔を持っていたなんて知らなかった。傍で役に立つことが喜びであったのに。首を振るわたしに半兵衛さまは微笑まれて、秀吉さまに仰った。
『この子に教え込んだ軍略は折り紙付きだ。彼女の采配は僕の采配だと思って聞いて欲しい。けど僕亡き後軽んじる者が出るかもしれない。だから、の身を立てておきたいんだ。彼女を竹中の養女にすることを認めて欲しい。――いいね、。竹中半兵衛が居なくとも君は竹中の保護下にある。不当な扱いはさせはしない。その智を豊臣の為に大いに揮っておくれ』
そうして半兵衛さまは、ごめんね女の子にこんなことを、と仰りながら弱弱しい手でわたしの頬を撫でられた。元々細身であられたけど指がひどく節くれだって病が恩師を連れ去ろうとしている事実を否が応にも突きつけられ、只々その御手に手を添えるしかなかったのだ。
それから数日で半兵衛さまは身罷られ、わたしの世界は紫黒になった。何も手に付かず口に入らず立ち上がろうと思うのにこの身が他人の物のように動かない。執務もそうだった。何も閃かず、兵站もまとまらず、そうすれば、うまくいかないの? と声を掛けてくれる半兵衛さまの姿が浮かんでは消え、鼻の奥がきな臭くなる。
そうして幻影に何故連れて行って下さらなかったのかと慟哭すれば、いつも無遠慮に腕を掴み上げる力がわたしを叱咤した。
『何をしている。豊臣の軍師が無様な姿を見せるな。鴨跖草殿の通名は飾りか? 哀哭する暇があるのならば戦え』
貫く言葉に、一番大切な人を失った苦しさは貴方には分からない。秀吉さまが亡くなったらそんなこと言える? と悪態を吐いた。彼は眉を顰め一言、不敬だ、と諌めるだけで怒りはしなかった。彼、石田三成は沈痛な顔をするもののそれほど平素と変わりなく、彼にとっては可愛がってくださったはずの半兵衛さまはその程度の存在でしかなかったのかとさらに哀しくなった。でも、彼は誤解されやすい人だった。幾日かした後、わたしは偶然見たのだ。彼の懐に紫水晶の数珠が仕舞われ、時折それを撫でていたのを。思い返せば近侍に持たせればよい書付を自ら持って来ていたのは彼なりの心配であったのかもしれない。
三成が居たからあの時自分は立ち直れた。半兵衛さまの理想の為、三成の密やかな献身への感謝の為、わたしは奮い立ち豊臣に尽くそうと思ったのだ。
でも、半兵衛さまを失った事実と時の流れというのは非情で、求心力が翳ったところを狙うように家康が離反した。沢山の兵に慕われた家康の造反は大量の戦力流出と地方支配の瓦解を招き、どうにかしようと献策や調略に奔走したがあの日が来てしまった。
豊臣と徳川の直接対決、絶対に負けてはならぬ初戦だった。その布陣は不気味で当時何度見返しても不安を払拭出来ずにいた。不確定要素のあるまま進軍するなど到底許されないからありのままを秀吉さまに進言し側近たちも止めに入った。だが、いつもはわたしの意見をお聞き入れになる秀吉さまがその日ばかりは頑としてお譲りになられなかった。
お出になってはなりません、この布陣は家康自ら囮になって秀吉さまを孤立させるものです。左腕をお信じ下さい。三成が必ず参ります。負けは出来ぬ戦いですが、此処で引いても豊臣軍は数で勝り、徳川はその隙を突いたにすぎません。一度引いて明日にでも攻勢をかければ相手は瓦解します。そう言っても首を縦にお振りにはなられずいつもの重厚のあるお声を持って拒否なされた。
『此処で引かば、半兵衛亡き後の豊臣は使い物にならぬと笑われ、それこそ勝利に身を固めて来た豊臣の威は地に堕ちよう』
本陣の者らは口々に、急いてはなりませんと言い、わたしは半兵衛さまの御名を出してまで制止したがやはり拒絶なされた。
『……よ、其方が半兵衛と我の間を語るのは許そう。なればこそ、其方に何かあっては我は半兵衛に申し訳が立たぬ』
覇王たる秀吉さまが垣間見せた情に怯まぬほうがどうかしている。切なさと大切にされている喜びが爆ぜ言葉に詰まるわたしを置いて秀吉さまは行ってしまわれた。すぐに本陣の手勢総てを秀吉さまに送り、三成にも知らせを出したが、悪い予感は当たってしまった。
馬を飛ばし秀吉さまと家康が居るであろう場所に着いた時、其処で見たのは本多忠勝に乗って飛び去る家康と、動かなくなった秀吉さまを抱えて慟哭する三成の姿だった。
「ああっ……」
あの時、もっと秀吉さまをお止めしていれば今頃はどうなっていたであろうか。三成まで私と同じ苦しみを味あわせずに済んだだろうか。三成を死なせて、わたしだけ家康の慕情でおめおめと生き残り、ましてや子供のように逃げて貞操を守ろうとするこの身の情けなさよ。
そもそも軍師として、何故家康の造反を見抜けなかったのか。無条件に家康を信用していた。彼はずっと一緒に居るのだと。どうしてそう思ってしまったのだろう。
半兵衛さま、わたしは何一つ貴方さまの想いにも恩にも報えていません。病であられた貴方さま程でないにせよ、日に当たらぬわたしの手は白くなりか細くなりました。こんな身では戦えない。このままでは本当に家康の思うがままにされてしまいます。
――。
嗚呼、なのに何故今耳に響くのは家康の声なのだろう。そんなに切なく呼ばないで。罪悪感と真摯を込めた目でわたしを見ないで。兵を持たぬわたしは心だけは百万の軍勢のつもりで挑まねばならないの。どんなに非難されたって望まれたってわたしの仰ぐ旗は五七の桐でなければいけないの。ひるんでは駄目。靡いては駄目。あの穏やかな容貌が豊臣を裏切ったのを忘れたか!
「あ……」
何度も首を振りそれでも脳裏を過ぎるのは戦でも執務でもない昼下がり。留守番の左近や刑部に手を振って城下を気ままに散策した娘らしい時間。三成が居て家康が居た。あの黄金の日々が戻ることを私はどこかで期待している。すでに友は冥道を逝ったというのに。
我知らず月を掴もうと手は格子の先へと延びる。月を掴んでも月白の友は戻らない。掴むことも出来ないのは永遠にあの幸せが戻らぬという事実を叩きつけるだけだった。
「半兵衛さま……秀吉さま……刑部……左近っ、三、成……」
今宵もわたしは声を殺して嗚咽する。皆の穏やかな顔が何度も巡り、最後で待つのはわたしを裏切った東照の顔だった。