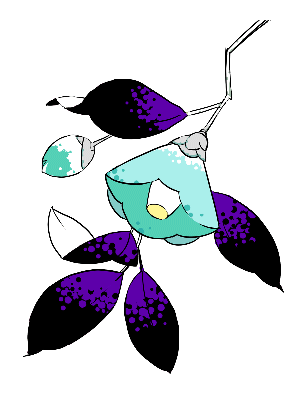
愛しいはずの人の名を奪い、自由を奪って二回目の春が過ぎようとしている。その間答えの出ない問いを何度となく続けてきた。拒絶される度に無意識に手に取った唐傘はすでにぼろぼろだ。今日も二の丸から退散したところだ。ワシはまた唐傘と共に今から咲き誇ろうとする桜を眺めている。
「家康様……」
「いいんだ」
彼女の拒絶は徹底していた。この二年、ワシはの顔をまともに見ていない。日常でも陣幕でも手放すことのなかった書も読まずただ過去を想いふける彼女は至極物音に敏感になったらしく、ワシの跫音を判別しすぐに奥の部屋に逃げ込んでしまうのだ。侍女らに指示すればその部屋の戸を開けるのは簡単で、あまりの拒絶ぶりに豊臣方のを快く思わない重臣たちからもそうしてはどうかとさえ言われた。でもワシは夢見ている。ただの一度でも、から顔を見せてくれることを。もう、それだけでいいと思えている。
「今日は藍白の打掛が美しかったな。雪輪に毬、梅、桜、後姿しか見えなかったがきっと二の丸殿に似合っているよ」
「家……」
「いいんだ!」
「……」
「いいんだ、本当に。ただ生きてくれてさえいれば」
無邪気に笑いあっていたあの頃、は屋敷で休息をとる時以外打掛を着ることはなかった。所作や調度品を見れば決して女性らしさを失ってはいなかったが、細身の躯体に鴨跖草(つきくさ)色の陣羽織を着、颯爽と歩く姿が印象に残る。彼女の笑みは力に傾倒する豊臣を、秀吉公や三成の心をいくらか和らげていたように思う。佇む彼女にはそういった華があった。半兵衛殿の傍で柔らかな表情をするをどれだけ追ったことだろう。
美しくて愛おしかった。
「また、嫌われてしまうな」
今日はに辛い報告をしに来たのだ。拒絶され直接伝えることは出来なかったが。いっそ知らない方が良いと考え直して侍女たちにもそう言い含めた。家康様、と沈痛な表情の才蔵に笑いかけてワシはまた表へと戻ることにした。広縁に散る石蕗の花弁の路が美しくも先の見えぬに対する不毛な恋を表すようで胸懐を抉る。ただ一度の恋はなんと甘く切なく辛いのか。
二の丸から戻るとそのまま主殿で休むのがもう日課と成り果てた。金雲雀の鈴虫にも似た啼き声が聞こえ、初夏には今少し遠い夜は肌寒さを感じさせる。今は秋なのかと惑わされてしまいそうだ。早く一人になりたくて近侍たちを下げてかなりの時を経た。装束も脱ぎ捨て聊か乱暴に着た白小袖はだらしなく、それも構わず柱に凭れ胡坐を掻くからなおさらだ。
「はあ……」
漏れ出でた溜息は思いの外疲労の色が濃い。江戸から駿府へ来る度に行われていた遣り取りと毎日行っているから余計か。思えば一人寝も板についたものだ。追っても追っても手の届かない恋をする天下人の褥は冷たく自分の体温以外で暖を取ることもない。組み敷きたいのではない、ただ寄り添ってくれたなら。分かっているのに、ワシはまだ諦めきれていないのだ。
「……ん?」
ふと衣擦れの音がした気がしてワシは耳を澄ました。それは空耳などではなく、足音も伴い広縁を通り、障子を抜け、障子の手前で止まる。才蔵か、忠次が火急の知らせでも持って来たかとも思ったがそれは武骨な音ではなかった。
「何かな?」
「……ぁ」
か細く聞こえたのは女の声だった。ああ、まただ、とワシは柱に頭を凭れ、外の漏れぬよう天井に息を吐いた。
、――二の丸殿がワシを受け入れないと城内で噂が立ってから、側室の座を狙う打算的な者や、家臣に言い含められた娘が十日と空けずに訪れるようになった。最早日常と成り果てたと言っていい。襖の向こうからはとても遠慮がちな、上様、と呼ぶ声がする。今宵はどちらの女だろうか、何時もは襖を開けることなく追い返すのだが今日は若干の苛立ちもあってか拝んでやろうと立ち上がる。無遠慮に戸を引けば、其処には深々と平伏し小さくなった娘の姿があった。
「……こんな夜更けに何の用だい?」
「あ、あの……」
娘は震えており、これは意に染まぬものを送り込まれたかと思い及ぶ。だが小袖の柄はそれ程上等ではなく口さがない上級侍女の一人とは言い難い。残念ながら身分違いと言わざるを得ない身なりだった。しかしその眸にひどく概視感を覚えた。
「う、上様、ご無礼お許しください……っ、」
お情けを、と紡ぐ唇はもどかしく上辺だけの演技には見えなかった。そんなものは日頃から見慣れ看破していたから。娘の眸は道ならぬ想いに苦しんでいる、それに尽きた。
「どなた様かの……代わりでいいのです。ただ、一夜……」
「……いけないよ。君の身体はそんな粗雑なものではない」
「……っ」
「一時の感情で捨ててはダメだ。捨てなければいけないのはその気持ちだよ」
「上様……」
「戻りなさい、ゆっくり休んでそんなものはなかったと思うんだ」
立て膝で娘に視線を合わせながら言う言葉はまるで自分に言い含めるように感じられる。娘の睫毛には滴が浮かびそれがむず痒く心を突く。
「……二の丸様、ですか?」
「ああ……」
瞼を閉じれば微笑むが蘇る。彼女の背には駿府城に咲く淡い花々ではなく、黄金に輝く大坂城の煌びやかさが見える。
「望んでも手に入らない恋、か。ワシも君も似た者同士だな」
「……っ、うえ、さま……」
「さあ、こんなところに居てはいけない。君の今後に関わる。ワシはどうにもしてやれないから」
それはたとえ噂が立っても召し上げることはない、という最後通牒だ。火消はしてもそれ以上はない、我ながら残酷な言葉だと思う。ワシも彼女もこの恋に折り合いを付けねばならぬのだ。そうせねば只々深みに嵌まり、何の解決も見いだせないまま時を食むだけだから。
深々と平伏した娘が足早に去り行く姿を見送りながら、それでもが来てくれていたならとまた不毛な想いに囚われ続けるのだ。
「ああ、……」
彼女はよく格子越しに月を見ているのだという。日輪も花も彼女の慰めだった。もうそれしか持たぬ彼女を気の毒だと思う。そしてその格子を張り巡らせているのは他ならぬ自分自身だ。様々な思惑から彼女を守る為との詭弁を付けてそうしているのだが結局は彼女が消えるのが怖かっただけだ。とらえて自由を奪って。でも手出しをしない。それで高潔なつもりかと笑えてくる。
今、この襖を抜け、少し強い口調を持って二の丸に乗り込み彼女を抱けば楽なのだと分かっているのだ。誰もが幸せになる。太平も、徳川の未来も、家臣の心も。ただ一人の心だけが水底に落とされたまま、否、ワシはどうなのだろう。三成も触れていないであろう彼女を思うさま扱えば想いを遂げたこと満足するのだろうか。
「三成は、……そうだろうな。だが……」
彼女の奥底に居る白藤の軍師は――。
「ばかなことを……」
それこそ不毛だ。こんな下卑た考えを浮かべるなど自分はどれだけ見下げた男なのだ。この気持ち誰にも気付かせてはならぬ。自分は絆を尊ぶ天下人なのだから。